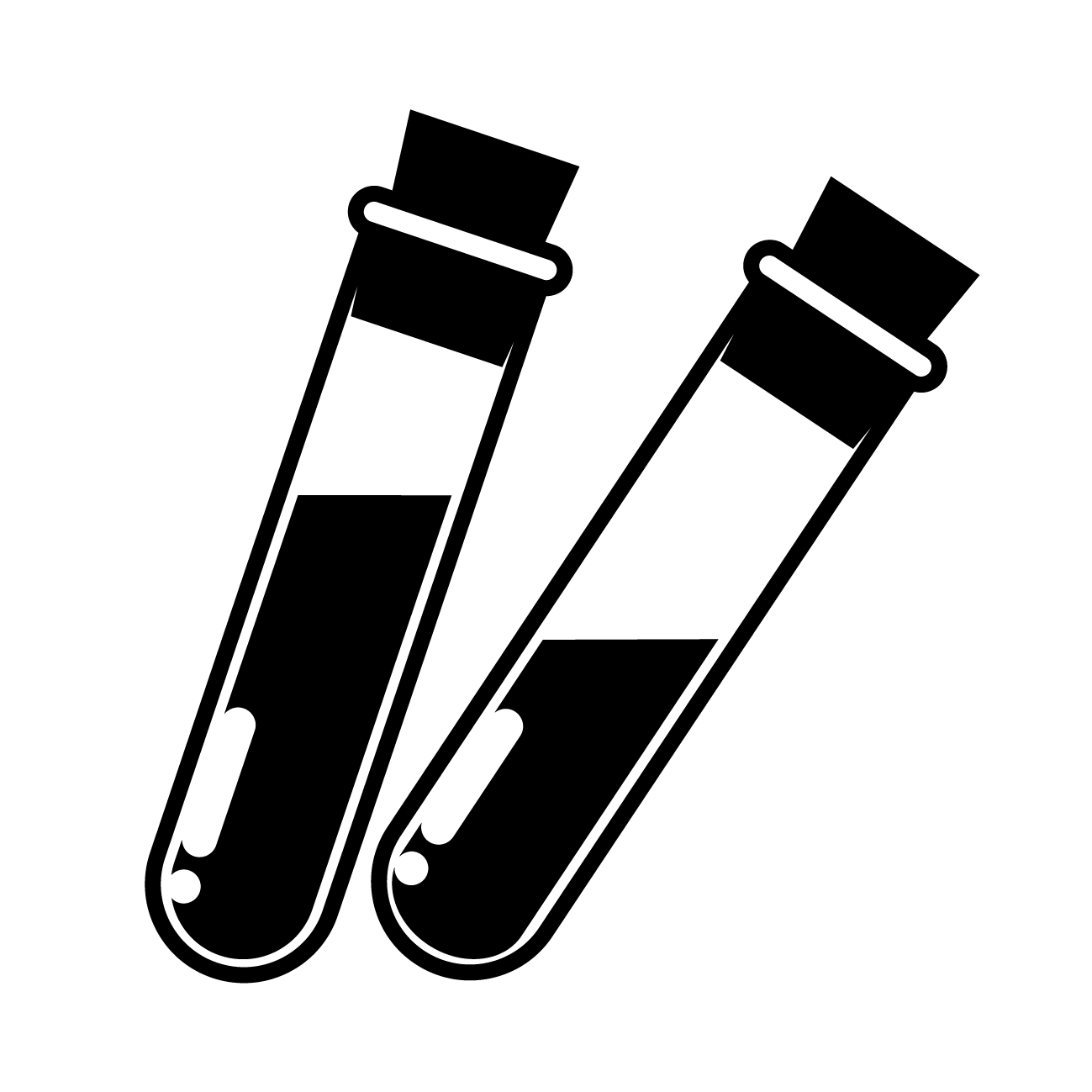いきなりですが、次に示す積分を計算してみて下さい。
式(1)\[ \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x}} \]
答えは「2」となります。正解できたでしょうか。
そしてどのように計算しましたか?
例えば次のような計算
式(2)\[ \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x}} = \int_0^1 2dt = 2 \]
これは \(t = \sqrt{1 - x}\) と置く置換積分を利用しています。
一見間違いなさそうな計算ですが、よく考えてみると被積分関数には定義できない点があることに気がつくでしょうか?
被積分関数の分母は0となってはいけないため \(x \char`≠ 1\) であるハズです。それにも関わらず、上記の積分計算では積分区間に \(x = 1\) を含んでしまっています。

グラフを描画してみても、曲線は \(x = 1\) に接近するに伴って無限大に大きくなるために、そもそも積分によって表される面積も無限大に発散してしまうのでは?とも。
しかしながら、現実として積分が実行でき積分値は2で間違いないのです。
実は上記の計算では省略された過程があり、ここでは正しい計算過程を踏むための新しい積分を導入することを考えて行きます。
広義積分
積分を計算するにあたって、定義できない点を含まれてしまっては困ります。
定義できない点を上手く回避して計算する方法を考えなければいけません。
そこで、次の図に示すように定義できない点から少しズラした点をとって考えてみましょう。

定量的に扱う必要があるので、ズラした量を \(\epsilon ~ (~ > 0 ~)\) と置いて、積分区間を \(0 \leq x \leq 1 - \epsilon\) とするのです。
すると図で示した青い領域の面積は積分で次のように記述されることになります。
式(3)\[ \int_0^{1 - \epsilon} \frac{dx}{\sqrt{1 - x}} \]
このようにすると積分区間内で定義できない点を含まないようにすることができたため、何も気にせずに積分の計算を実行することができるようになります。
式(4)\[ \biggl[ - 2 \sqrt{1 - x} \biggr]_0^{1 - \epsilon} = -2 \sqrt{\epsilon} + 2 \]
そして、もともと積分区間は \(0 \leq x < 1\) であったことから \(\epsilon \rightarrow 0\) の極限を考えれば良く
式(5)\[ -2 \sqrt{\epsilon} + 2 ~ \rightarrow ~ 2 ~~~ (~ \epsilon \rightarrow 0 ~) \]
結果として積分値が2となることが示されるのです。
以上の内容を再度数学的に明示し直すと次のようになります。
式(6)\[ \int_0^{\textcolor{red}{1}} \frac{dx}{\sqrt{1 - x}} = \textcolor{red}{\lim_{\epsilon \rightarrow +0}} \int_0^{\textcolor{red}{1 - \epsilon}} \frac{dx}{\sqrt{1 - x}} \]
このように式(6)の左辺では積分区間の上端が被積分関数に置いて定義されていない点になっており、そういった場合には極限を利用して書き直すという作業が必要になります。
こういった積分を拡張されたという意味を踏まえて広義積分と呼びます。
逆に、被積分関数で定義されていない点を積分区間に含めるというのは、案に広義積分を実行しなさいという意味と捉えることも可能であり、実際そのように簡略化されている場合もあるので注意が必要です。
また積分区間の上端あるいは下端にではなく、その間に定義できない点を含む場合には、その点を境界として2つの積分に分けることによって計算するようにします。
例えば、分数関数 \(\frac{1}{x - 1} ~ (x \char`≠ 1)\) を \(0 \leq x \leq 2\) で積分する場合、数学的には次のとおりに書くことになります。
式(7)\[ \begin{align*} \int_0^2 \frac{dx}{x - 1} &= \int_0^1 \frac{dx}{x - 1} + \int_1^2 \frac{dx}{x - 1}\\[15pt] &= \lim_{\epsilon_1 \rightarrow +0} \int_0^{1 - \epsilon_1} \frac{dx}{x - 1} + \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0} \int_{1 + \epsilon_2}^2 \frac{dx}{x - 1} \end{align*} \]
無限積分
広義積分の導入によって、積分区間を動的に定めることができるようになりました。
しかし広義積分の説明は、ここでまた新たに導入する無限積分を説明するための前置きに過ぎません。
結論からお話すると、無限積分とは積分区間の上端あるいは下端に無限大 \(\pm \infty\) を含む積分計算を指します。
例えば、次に示す関数の無限積分を考えてみましょう。
式(8)\[ \int_0^{\infty} e^{-x} dx \]
無限大は本来極限を利用して記述されるため、次のように書かれることもあります。
式(9)\[ \lim_{c \rightarrow \infty}\int_0^c e^{-x} dx \]
計算方法自体は何も難しいことはなく、原始関数を求めたのち、与えられた積分区間の上端と下端を変数に代入するだけです。
式(10)\[ \int_0^c e^{-x} dx = \biggl[ -e^{-x} \biggr]_0^c = 1 - e^{-c} \]
あとは \(c \rightarrow \infty\) の極限をとれば良く、結果積分値は1になることが分かります。
式(11)\[ 1 - e^{-c} ~ \rightarrow ~ 1 ~~~ (~ c \rightarrow \infty ~) \]
この積分計算をグラフで示すと次のようになります。

この例のように、無限積分は実行するにあたって少なくとも曲線が0に収束しているような都合の良い関数でしか利用できないことが推測されます。
しかし、曲線が0に向かっているのにも関わらず積分値が得られない(すなわち収束しない)ような関数もあります。
例えば分数関数 \(\frac{1}{x}\) はそれに当たります。適当に積分区間を設けて実際に計算してみると無限大に発散してしまうことが分かるでしょう。
式(12)\[ \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \biggl[ \log x \biggr]_0^{\infty} = \log (\infty) - \log 1 = \infty \]
このように必ずしも無限積分で積分値が得られるとは限らないため、実際に計算して確認してみるほか無いでしょう。
ガウス積分
無限積分を利用した非常に重要な公式があります。
式(13)\[ \int_0^{\infty} e^{-ax^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \]
被積分関数 ( \(a = 1\) の場合) をグラフで示したものが次の図になります。

グラフを見ても \(x\) の増加に伴って0に収束していることから、無限積分が実行できる可能性は満たしています。
しかし、この積分を計算しようとするとすぐさま問題に直面することになるのです。
実際に取り組んでみていただければ分かりますが、原始関数が簡単に求められないことに気がつくでしょう。
一体どのように計算して式(13)右辺の結果を導くというのか以下で示していきます。
巧妙な扱いと変数変換
式(13)の無限積分を解くにあたり、実に巧妙な手口を利用するのですが、筆者の経験上この積分以外で用いたことはありません。
ただ、被積分関数にバリエーションがあったり積分区間が異なる場合など、状況によって現れ方が様々なので計算結果を覚えるより計算方法を習得することに専念するほうが良いかと思われます。
それでは早速進めていきますが、その手口とはまず式(13)とは別に次に示す積分を持ち出すというのです。
式(14)\[ \int_0^{\infty} e^{-ay^2} dy \]
単に式(13)左辺の \(x\) を \(y\) に変えただけと言えばその通りで、式(13)とは別に持ち出したと言えど、積分変数に何を用いたところで結果は同じなので、現状何がしたいのかと思われるかもしれません。
ひとまず式(13)と式(14)について、新たに積分値を \(I\) で表現しておくことにします。
式(15)\[ I \equiv \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-ay^2} dy \]
ここまでは式(13)を解くための下準備に過ぎませんでしたが、以降が本節の要旨となります。
それは式(13)および式(14)の積を考えるところから始まります。
式(16)\[ I^2 = \left( \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx \right) \left( \int_0^{\infty} e^{-ay^2} dy \right) \]
また求めたい値である積分値 \(I\) は2乗で表すことができます。
式(16)は被積分関数の変数がそれぞれ \(x\) のみ、また \(y\) のみという形でキレイに分離できた累次積分であることに気がつくでしょうか。
これを一度組み替え直して次のように表現してみることを考えます。
式(17)\[ \begin{align*} I^2 &= \int_{x = 0}^{\infty} \int_{y = 0}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-ay^2} dxdy \\[15pt] &= \int_{x = 0}^{\infty} \int_{y = 0}^{\infty} e^{-a(x^2 + y^2)} dxdy \end{align*} \]
式を整理してみたは良いものの、被積分関数を求めたいという目的を果たすためにもう少し式変形を施しましょう。
それには、極表示を利用した変数変換を利用します。
式(18)\[ x = r \cos \theta \\[15pt] y = r \sin \theta \]
ここで \(r\) とは原点からの距離であり、\(\theta\) とは \(xy\) 平面上における角度を表します。
また、積分計算時に変数変換(置換積分)するときに注意しなければならないことに次の2点があります。
- 微小量の変化
- 積分区間の変化
1点目について、2重積分の場合は微小面積 \(dxdy\) を指しますが、これは極座標に置いては \(rdrd\theta\) に書き換える必要があります。
続いて2点目の積分区間について、これは作図して考えてみると理解しやすいでしょう。

\(x\) は0から無限大の間を変化でき、かつ \(y\) は0から無限大の間を変化できることから、積分領域は \(xy\) 平面上における第1象限のみと言えます。
そしてこの領域は極座標では \(0 \leq r \leq \infty\) かつ \(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\) と表現すれば良いですね。
したがって、以上の2点を踏まえると式(17)は極座標において次のように表式へ式変形されます。
式(19)\[ I^2 = \int_{r = 0}^{\infty} \int_{\theta = 0}^{\frac{\pi}{2}} re^{-ar^2} drd\theta \]
すこし手の混んだ手続きを踏んで来ましたが、実は式(19)は簡単に積分が実行できる様になっているのです。
まずはすぐに積分を実行できる \(\theta\) 成分から見てみましょう。被積分関数に \(\theta\) が含まれていないので、単に定数が掛かる結果となります。
式(20)\[ \begin{align*} I^2 &= \int_{\theta = 0}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{r = 0}^{\infty} re^{-ar^2} dr \\[15pt] &= \frac{\pi}{2} \int_{r = 0}^{\infty} re^{-ar^2} dr \end{align*} \]
更に \(r\) についても原始関数を簡単に求めることができ
式(21)\[ \begin{align*} I^2 &= \frac{\pi}{2} \int_{r = 0}^{\infty} re^{-ar^2} dr \\[15pt] &= \frac{\pi}{2} \biggl[ -\frac{1}{2a} e^{-ar^2} \biggr]_0^{\infty} \\[15pt] &= \frac{\pi}{4a} \end{align*} \]
が得られます。
求めたいのは \(I\) であるから平方根をとれば、式(13)と同じ結果になることが分かります。
\[ I = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \]
【サイト運営 : だいご】
今年で物理化学歴13年目になります。
大学入試2次数学でたった3割しか得点できなかったいわゆる数弱落ちこぼれ。それでも好きこそものの上手なれと言ったところか、学会で最優秀賞受賞したり首席卒業できてしまったので、役に立つ知識を当サイトに全て惜しみなく公開しようと思います。ブックマークをオススメ。