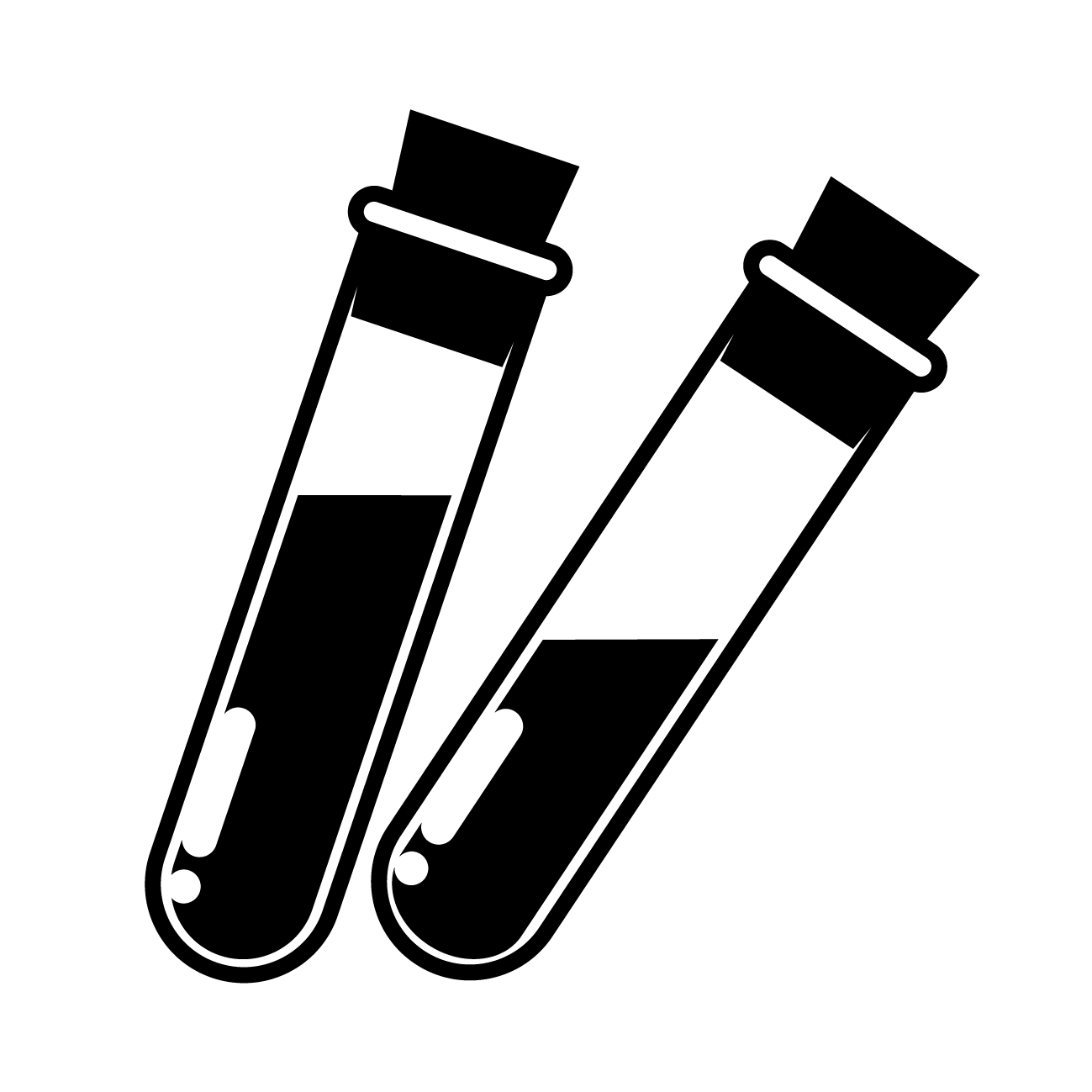化学反応系の平衡状態を記述する量として平衡定数を定義し、気体反応系や溶液系に適用して求めていきます。
また、化学反応系に対する熱力学の適用していく方法についても触れていきます。ここは一般に触れられることが少なく、行間を埋める内容となるでしょう。
■目次■
化学平衡
化学平衡の基本概念
反応容器に加えられた複数の化学種は反応を起こすことによって反応前の状態と反応後の状態といった2つないしは複数の状態を取りえます。
反応後の系の状態を観察したとき、見かけ上の変化は確認できない、いわゆる安定した状態を保っています。
このような安定した状態は化学反応系における平衡状態ということで化学平衡と呼ばれます。
簡単な例として次のような化学反応系を考えてみましょう。
\[ \text{A} \rightleftarrows \text{B} \]
こちらの化学反応は、化学種Aから化学種Bへ、逆に化学種Bから化学種Aへ変化することを表しています。
上記の記述の場合、化学種Aから化学種Bへの変化を正反応、化学種Bから化学種Aへの変化を逆反応と呼んで区別します。
これらの反応は停止することなく、絶えず \(\text{A} \rightarrow \text{B}\) および \(\text{A} \leftarrow \text{B}\) の変換が同時に生じています。
そして正反応と逆反応ともにつり合っているとき、化学反応系には見かけ上の変化が観察されない化学平衡状態にあると結論できます。
化学反応の進行度
適切な量で混合された水素と酸素を燃焼させれば、完全に反応して水が生成されることはご存知かと思われます。化学反応式では下記の通り。
\[ 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{H}_2\text{O} \]
逆に水が自然に水素と酸素に分解することはなく、水を安全に利用することができます。
このような一方通行の化学反応を不可逆反応と呼びます。
他方、逆反応も起こり得る反応もあり可逆反応と呼びます。
例えばアンモニアの生成反応では、反応物および生成物が特定の割合だけ存在する平衡状態に落ち着きます。
\[ \text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftarrows 2\text{NH}_3 \]
アンモニアの生成を例とした可逆反応では、分かりやすく言うと反応進行が途中で止まってしまうために、期待する量の目的生成物が得られません。
実際にどの程度反応が進行したかを表す量として反応進行度 \(\xi\) なるものを定義するのが便利です。
次に示す化学反応系を考えます。
\[ \nu_1 \text{A}_1 + \nu_2 \text{A}_2 + \cdots + \nu_r \text{A}_r ~ \rightleftarrows ~ \nu_{r + 1} \text{A}_{r + 1} + \nu_{r + 2} \text{A}_{r + 2} + \cdots + \nu_{r + s} \text{A}_{r + s} \]
ここで \(\text{A}_i\) は \(i\) 番目の化学種、\(\nu_i\) は化学反応系における \(\text{A}_i\) の化学量論係数です。
ただし、化学量論係数 \(\nu_i\) は数学的に用いる際、反応物か生成物かで符号が分かれることに注意して下さい。
- 反応物 ( 反応式 左辺 ) : 化学量論係数は負号 \(\nu_i < 0\)
- 生成物 ( 反応式 右辺 ) : 化学量論係数は正号 \(\nu_i > 0\)
さて、この化学反応系に対して反応進行度を定義していきます。
初期状態、すなわち一連の反応が開始するまでの時点における化学種 \(\text{A}_i\) の物質量を \(n_{i0}\)、\(\xi\) だけ反応が進行した時点における化学種 \(\text{A}_i\) の物質量を \(n_i\) とするとき、反応進行度 \(\xi\) を次式で定義します。
\[ \xi \equiv \frac{n_i - n_{i0}}{\nu_i} \]
反応進行度の定義式(1)を \(n_i = n_{i0} + \nu_i \xi\) と書き直すとその意味を把握しやすいかもしれません。
要は反応進行度 \(\xi\) によって化学種 \(\text{A}_i\) の物質量 \(n_i\) が化学量論係数 \(\nu_i\) の比率で変化することを表す式に過ぎません。
また反応進行度 \(\xi\) には、化学種に依存せず化学反応系に対して1つに定まる量であることに注意です。物質量を化学量論係数で割ることによって、全ての化学種 \(\text{A}_i\) について統一的に扱うことができるようになっています。
また"反応進行度"と呼ばれるため、0 から 1 の値しか取らないと誤解する恐れがありますが、反応進行度の次元 ( 単位 ) は \([\text{mol}]\) であり、化学量論係数が 1 である物質を基準として初期状態から反応物がどのくらい減少したか、また生成物がどのくらい増加したかを物質量単位で教えてくれる量である事も漏れなく理解しておきましょう。
化学平衡の熱力学的観点
可逆的な化学反応系では、温度や圧力などの条件さえ一致していれば、いつ誰が実験を行っても同じ反応進行度 \(\xi\) までしか反応が進みません。
これは化学反応系が何らかの法則によって支配されているからで、すぐ後で明かすように平衡定数と呼ばれる温度や圧力の条件によって規定される量によって説明されます。
平衡定数は化学反応系へ熱力学を適用して解析を進めると得られるのですが…問題となるのは熱力学の適用方法です。
続く内容で、まずは熱力学から化学への橋渡しを行った後、平衡定数の確認まで一挙に解説していきます。
化学反応系に熱力学を適用する方法
任意の化学反応系に対して、熱力学第一法則を適用していきます。
熱力学第一法則は、系の内部エネルギー変化 \(dU\) を系外への仕事量 \(\delta W\) と外部環境からの吸熱量 \(\delta Q\) によって簡潔に説明してくれます。
\[ dU = \delta Q - \delta W \]
ここで準静的過程において、仕事量 \(\delta W\) は、外界から掛かる圧力と系の体積変化の積 \(PdV\) で置き換えられ、吸熱量 \(\delta Q\) は外部環境の温度と系のエントロピー変化の積 \(TdS\) で置き換えられます。
\[ dU = TdS - PdV \]
熱力学第一法則の意味するところは、エネルギー保存の法則であり式(2)あるいは式(3)の限りではありません。
いま着目している化学反応によるエネルギー変化を組み込んだエネルギー保存を考えて、化学反応系に熱力学を適用してみましょう。
化学反応の進行、すなわち反応進行度の変化 \(d\xi\) によって系のエネルギーが減少するとして \(-Ad\xi\) を式(3)に組み込みます。
\[ dU = TdS - PdV - Ad\xi \]
もちろん単に式(3)に \(-Ad\xi\) の項を加えたのではなく、何度も言うように熱力学第一法則はエネルギー保存の関係を表しているので、化学反応によるエネルギー変化の導入に伴って \(TdS\) および \(PdV\) も式(3)のときと比較して値は変化しています。
また \(A\) は以下で示すように、系のエネルギーの反応進行度に関する偏微分係数です。
内部エネルギー \(U(S, ~ V, ~ \xi)\) の全微分は
\[ dU = \left( \frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, ~ \xi} dS + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, ~ \xi} dV + \left( \frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{S, ~ V} d\xi \]
であるから、式(4)と比較することで直ちに次式が得られます。
\[ A = -\left( \frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{S, ~ V} \]
化学反応によって系に生じる変化を知るには、系のエネルギーの反応進行度に関する偏微分係数を調べる事になりますが、内部エネルギーを選択してしまうと系のエントロピーと体積を固定するという条件を設ける必要があり、エントロピーを固定する方法について別の問題が生じてしまいます。
そこで、内部エネルギーの代わりにギブス自由エネルギーを利用します。
一般に化学反応が等温定圧条件下で行われることが多く、ギブス自由エネルギーは制御変数に温度および圧力を持つため化学反応系の解析時には好都合です。
実際に、ギブス自由エネルギーの定義式 \(G = U + PV - TS\) の全微分は
\[ dG = dU + VdP + PdV - SdT - TdS \]
であり、式(4)から \(dU\) を消去して整理すると次式が得られます。
\[ dG = VdP - SdT - Ad\xi \]
等温定圧条件 \(dT = 0, ~ dP = 0\) とすれば、系のギブス自由エネルギー変化が直接化学反応によるエネルギー変化に等しくなります。
\[ dG = - Ad\xi \]
また、ギブス自由エネルギー \(G(T, ~ P; ~ \xi)\) の全微分
\[ dG = \left( \frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, ~ \xi} dT + \left( \frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, ~ \xi} dP + \left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} d\xi \]
と、式(8)とを比較すると反応進行度の項について直ちに次の関係が得られます。
\[ A = -\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} \]
その他、系のエネルギーを記述する際、ヘルムホルツ自由エネルギー \(F\) やエンタルピー \(H\) がありますが、上記の展開同様に行えばエネルギーの反応進行度に関する偏微分係数は全て等しい関係が導かれます。
\[ A = -\left( \frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{S, ~ V} = -\left( \frac{\partial F}{\partial \xi} \right)_{T, ~ V} = -\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} = -\left( \frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{P, ~ S} \]
それぞれ状況に応じて適切なエネルギーを利用するようにしましょう。
※とは言え、内部エネルギーとエンタルピーは、エントロピーを固定する条件が必要になるので、主にヘルムホルツ自由エネルギーかギブス自由エネルギーを利用することになるでしょう。
化学平衡定数の導出
化学反応が生じる系の情報は、ギブス自由エネルギーの反応進行度に関する偏微分係数が教えてくれます。
次の化学反応系について考えましょう。
\[ \nu_1 \text{A}_1 + \nu_2 \text{A}_2 + \cdots + \nu_r \text{A}_r ~ \rightleftarrows ~ \nu_{r + 1} \text{A}_{r + 1} + \nu_{r + 2} \text{A}_{r + 2} + \cdots + \nu_{r + s} \text{A}_{r + s} \]
この化学反応系は、\(r + s\) 種の異なる成分が同時に存在するような多成分系です。
多成分系では、系全体のギブス自由エネルギーが成分 \(i\) の物質量 \(n_i\) と化学ポテンシャル \(\mu_i\) の積の和で与えられ次式のように記述されます。
\[ G(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) = \sum_{i = 1}^{r + s} n_i \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) \]
ここで \(\boldsymbol{n}\) は全ての成分の物質量の組であり、\((n_1, ~ n_2 ~ \cdots ~ n_{r + s})\) という組の記述を簡略化した記号です。
また式(13)中の化学ポテンシャルは、単成分系の化学ポテンシャル \(\mu_i(T, P)\) ではなく、自身の周囲に存在する異なる成分の影響を受けることに注意してください。
式(13)を反応進行度で偏微分していきます。
\[ \left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} = \left( \frac{\partial}{\partial \xi} \sum_{i = 1}^{r + s} n_i \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) \right)_{T, ~ P} \]
反応進行度は式(1)で定義したように、物質量と依存関係にあることに注意して計算を行っていきます。
\[ \begin{align*} \text{eq(15.1) : } ~~~~~ &\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} &&= \left( \frac{\partial}{\partial \xi} \sum_{i = 1}^{r + s} n_i \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) \right)_{T, ~ P} \\[15pt] \text{eq(15.2) : } ~~~~~ &&&= \sum_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{\partial n_i}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) + \sum_{i = 1}^{r + s} n_i \left( \frac{\partial \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n})}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} \\[15pt] \text{eq(15.3) : } ~~~~~ &&&= \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) + \sum_{i = 1}^{r + s} n_i \left( \frac{\partial \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n})}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} \end{align*} \]
式(15.2)の \(\left( \frac{\partial n_i}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P}\) は、\(n_i = n_{i0} + \nu_i \xi\) の関係を利用して計算すれば化学量論係数 \(\nu_i\) に等しいことが分かります。
また、系の示強変数はギブス・デュエムの式によって拘束条件が与えられているので、式(15.3)の2つ目の和の項は 0 になります。
ギブス・デュエムの式は次式で与えられ…
\[ \begin{gather*} SdT - VdP + \sum_{i} n_id\mu_i = 0 ~ \xrightarrow{\substack{dT = 0 \\[3pt] dP = 0}} ~ \sum_{i} n_id\mu_i = 0 \\[20pt] \therefore ~ \sum_{i} n_i \frac{\partial \mu_i}{\partial q} = 0 \end{gather*} \]
任意の変数 \(q\) の変化について、化学ポテンシャル変化の項は 0 となります。
結局、式(15)は次のように整理されます。
\[ \left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} = \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) \]
この式(16)を用いることで、平衡定数を導くことができます。
混合気体の場合
気体のみの化学反応系について、複数成分が存在する際 それぞれの成分の化学ポテンシャルは次式で与えられます。
\[ \mu_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) = \mu_i(T, ~ P^\circ) + RT\ln \frac{P_i}{P^\circ} \]
ここで \(P_i\) は成分 \(i\) の分圧、\(P^\circ\) は標準圧力で \(1 ~ [\text{bar}] = 1.013 \times 10^5 ~ [\text{Pa}]\) を表しています。
式(17)を式(16)に代入して整理していきます。
\[ \begin{align*} \text{eq(18.1) : } ~~~~~ &\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} &&= \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \left\{ \mu_i(T, ~ P^\circ) + RT\ln \frac{P_i}{P^\circ} \right\} \\[15pt] \text{eq(18.2) : } ~~~~~ &&&= \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \mu_i(T, ~ P^\circ) + RT \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \ln \frac{P_i}{P^\circ} \\[15pt] \text{eq(18.3) : } ~~~~~ &&&= \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}_i^\circ + RT \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \ln \frac{P_i}{P^\circ} \end{align*} \]
式(18.3)では、単成分化学ポテンシャル \(\mu_i(T, ~ P)\) がモルギブス自由エネルギー \(\bar{G}_i\) と等しいことを利用しています。
そして標準圧力下における標準モルギブス自由エネルギー \(\bar{G}_i^\circ ~ \big( = G_i(T, ~ P^\circ) \big)\) は化学便覧などに温度別でまとめられている数値を利用できます。
また式(18.3)の2つ目の和の項について対数法則を用いて次のように変形します。
\[ RT \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \ln \frac{P_i}{P^\circ} ~ = ~ RT \sum_{i = 1}^{r + s} \ln \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} ~ = ~ RT \ln \prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} \]
式(18.3)および式(19)から、次式が得られます。
\[ \left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} = \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}_i^\circ + RT \ln \prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} \]
さて式(20)から、ある温度について着目したとき標準モル自由エネルギー \(\bar{G}_i^\circ\) は成分固有の定数となるので、系のギブス自由エネルギーの反応進行度に関する偏微分係数 \(\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P}\) は気体の分圧 \(P_i\) のみに依存する事が分かります。
言い換えると、系の反応進行度は 各気体成分の分圧で表されるということです。
この化学反応系が平衡状態にあるとき、系のギブス自由エネルギー変化は 0 でなければならないので
\[ 0 = \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}_i^\circ + RT \ln \prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} \]
を満たす必要があります。
このとき式(21)中の \(\prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i}\) は、ある一定値をとることになるので、改めて \(K_P\) と置くことにしましょう。
\[ K_P = \prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} = \text{Const.} ~~~ ( ~ \text{equilibrium state} ~ ) \]
\(K_P\) は平衡状態における系の成分比を与えており、こちらが平衡定数になります。また圧力に関する平衡定数であるため、圧平衡定数と呼ばれることもあります。
また式(22)のとおり平衡定数は各成分に対して標準圧力との比を考え それらの積を計算します。このことから平衡定数は無次元であることが分かります。
式(21)を圧平衡定数について解くと次のようになります。
\[ \begin{gather*} \ln K_P = - \frac{1}{RT} \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}_i^\circ \\[15pt] \therefore ~ K_P = \exp \bigg[ - \frac{1}{RT} \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}_i^\circ \bigg] \end{gather*} \]
したがって、化学反応を生じ得る混合気体の系では、式(23)を満たすようにそれぞれの気体成分の分圧 \(P_i\) が定まることが分かります。
標準モルギブス自由エネルギー \(\bar{G}_i^\circ\) の温度依存性も考慮すれば、平衡定数のより詳細な表式を得ることができます。
モルギブス自由エネルギー \(\bar{G}_i(T, ~ P)\) 、もしくは単成分化学ポテンシャル \(\mu_i(T, ~ P)\) が次式で記述されることを利用します。
\[ \bar{G}_i(T, ~ P) = \mu_i(T, ~ P) = RT - RT \ln \bigg[ \left( \frac{T}{T_0} \right)^{\alpha + 1} \frac{P^\circ}{P_i} \bigg] + \bar{U}_i(T, ~ P^\circ) - T\bar{S}_i(T_0, ~ P^\circ) ~~~ \left( ~ \bar{U}_i = \frac{U}{n_i}, ~ \bar{S}_i = \frac{S}{n_i} ~ \right) \]
式(24)から、標準モルギブス自由エネルギー \(\bar{G}_i^\circ\) は式中の圧力を \(P = P^\circ\) とした次式で与えられます。
\[ \bar{G}_i^\circ = \bar{G}_i(T, ~ P^\circ) = RT - RT \ln \bigg[ \left( \frac{T}{T_0} \right)^{\alpha + 1} \frac{P^\circ}{P_i} \bigg] + \bar{U}_i(T, ~ P^\circ) - T\bar{S}_i(T_0, ~ P^\circ) \]
式(25)を式(23)に代入して、
\[ K_P = \exp \Bigg[ - \frac{1}{RT} \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \left\{ RT - RT \ln \bigg[ \left( \frac{T}{T_0} \right)^{\alpha + 1} \frac{P^\circ}{P_i} \bigg] + \bar{U}_i(T, ~ P^\circ) - T\bar{S}_i(T_0, ~ P^\circ) \right\} \Bigg] \\[15pt] = \exp \Bigg[ - \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \left\{ 1 - \ln \bigg[ \left( \frac{T}{T_0} \right)^{\alpha + 1} \frac{P^\circ}{P_i} \bigg] + \frac{\bar{U}_i(T, ~ P^\circ)}{RT} - \frac{\bar{S}_i(T_0, ~ P^\circ)}{R} \right\} \Bigg] \\[15pt] \]
が得られます。
溶液の場合
式(16)に戻って、今度は溶液中に存在する成分の化学ポテンシャルを代入することによって、溶液系における平衡定数を得ることができます。
溶液中に存在する成分の化学ポテンシャルは、溶媒と溶質でそれぞれ次式で与えられます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln a_1 \]
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln a_i ~~~ \big( ~ i ~ \char`≠ ~ 1 ~ \big) \]
ここで \(a_i\) は成分 \(i\) の活量を表しています。以下 \(i = 1\) を溶媒、その他を溶質とします。
式(28)中の \(\mu_i^\circ(T, ~ P)\) は、化学ポテンシャルと同じ次元を持つ量で具体的には次式で与えられます。
\[ \mu^\circ_i(T, ~ P) \equiv \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{H_i}{P^*_i} \]
式中の \(H_i\) は成分 \(i\) のヘンリー定数、\(P_i^*\) は純粋成分 \(i\) の蒸気圧です。
式(16)に式(27)および式(28)を代入して整理していきます。
\[ \begin{align*} \text{eq(29.1) : } ~~~~~ &\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} &&= \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) \\[15pt] \text{eq(29.2) : } ~~~~~ &&&= \nu_1 \left\{ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln a_1 \right\} + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \left\{ \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln a_i \right\} \\[15pt] \text{eq(29.3) : } ~~~~~ &&&= \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^\circ_i(T, ~ P) \right\} + RT \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \ln a_i \\[15pt] \text{eq(29.3) : } ~~~~~ &&&= \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^\circ_i(T, ~ P) \right\} + RT \ln \prod_{i = 1}^{r + s} a_i^{\nu_i} \end{align*} \]
この溶液系が平衡状態にあるとき、\(\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} = 0\) であり、その時の平衡定数を
\[ K = \prod_{i = 1}^{r + s} a_i^{\nu_i} \]
としておくと、式(29.3)は
\[ \begin{gather*} 0 = \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^\circ_i(T, ~ P) \right\} + RT \ln K \\[15pt] \ln K = -\frac{1}{RT} \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^\circ_i(T, ~ P) \right\} \\[15pt] \therefore ~ K = \exp\Bigg[ -\frac{1}{RT} \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^\circ_i(T, ~ P) \right\} \Bigg] \end{gather*} \]
が得られます。
理想希薄溶液を考えて、実用的な理論を導きます。
理想希薄溶液では、溶媒および溶質の活量はモル分率に近づいて
\[ \begin{align*} a_1 &\rightarrow x_1 \\[15pt] a_i &\rightarrow x_i \end{align*} \]
さらに溶媒は溶質と比べて過剰に存在し、物質量の大小関係は \(n_1 \gg n_i\) であるため、溶媒および溶質のモル分率はそれぞれ次のようになります。
\[ \begin{align*} x_1 &= \frac{n_1}{n_1 + n_2 + \cdots} \rightarrow 1 \\[15pt] x_i &= \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \cdots} \rightarrow \frac{n_i}{n_1} = \frac{C_i}{C_1} \end{align*} \]
溶液系では、物質量ではなくモル濃度がよく利用されるので \(x_i = \frac{C_i}{C_1}\) としました。
以上、式(32)および式(33)を考慮して、もう一度 平衡定数を導きます。
溶媒および溶質の化学ポテンシャルの式(27), (28)に戻って…
\[ \begin{align*} \text{eq(34.1) : } ~~~~~ &\mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) &&= \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln a_1 ~~~ ( ~ = \text{eq(27)} ~ )\\[15pt] \text{eq(34.2) : } ~~~~~ &\rightarrow ~ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) &&\simeq \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) \end{align*} \]
\[ \begin{align*} \text{eq(35.1) : } ~~~~~ &\mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) &&= \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln a_i ~~~ ( ~ = \text{eq(28)} ~ )\\[15pt] \text{eq(35.2) : } ~~~~~ &\rightarrow ~ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) &&\simeq \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{C_i}{C_1} \\[15pt] \text{eq(35.3) : } ~~~~~ &&&= \textcolor{red}{\mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{C^\circ}{C_1}} + RT \ln \frac{C_i}{C^\circ} \\[15pt] \text{eq(35.4) : } ~~~~~ &&&= \textcolor{red}{\tilde{\mu}_i(T, ~ P)} + RT \ln \frac{C_i}{C^\circ} \end{align*} \]
ここで新たに化学ポテンシャルと同じ次元を持つ \(\tilde{\mu}_i(T, ~ P)\) を次式で定義しました。
\[ \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \equiv \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{C^\circ}{C_1} \]
式(34.2)および式(35.4)を式(16)に代入して整理します。
\[ \begin{align*} \text{eq(37.1) : } ~~~~~ &\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} &&= \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) \\[15pt] \text{eq(37.2) : } ~~~~~ &&&= \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \left\{ \tilde{\mu}_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{C_i}{C^\circ} \right\} \\[15pt] \text{eq(37.3) : } ~~~~~ &&&= \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \right\} + RT \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \ln \frac{C_i}{C^\circ} \\[15pt] \text{eq(37.4) : } ~~~~~ &&&= \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \right\} + RT \ln \prod_{i = 2}^{r + s} \left( \frac{C_i}{C^\circ} \right)^{\nu_i} \end{align*} \]
系が平衡状態にあるとき、\(\left( \frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, ~ P} = 0\) を満たします。
\[ 0 = \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \right\} + RT \ln \prod_{i = 2}^{r + s} \left( \frac{C_i}{C^\circ} \right)^{\nu_i} \]
このとき次の平衡定数を定めます。
\[ K_C \equiv \prod_{i = 2}^{r + s} \left( \frac{C_i}{C^\circ} \right)^{\nu_i} \]
\(K_C\) は溶液系における平衡定数で明示的に濃度平衡定数と呼ぶこともあります。
式(39)を式(38)に代入して \(K_C\) について解くと次式が得られます。
\[ \begin{gather*} \ln K_C = -\frac{1}{RT} \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \right\} \\[15pt] \therefore ~ K_C = \exp \Bigg[ -\frac{1}{RT} \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \right\} \Bigg] \end{gather*} \]
平衡定数の計算
平衡定数を計算して求めてみましょう。
圧平衡定数 \(K_P\) と濃度平衡定数 \(K_C\) は次式で与えられます。
\[ \begin{align*} K_P &= \prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} = \exp \bigg[ -\frac{1}{RT} \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}^\circ_i \bigg] \\[15pt] K_C &= \prod_{i = 2}^{r + s} \left( \frac{C_i}{C^\circ} \right)^{\nu_i} = \exp \Bigg[ -\frac{1}{RT} \left\{ \nu_1 \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + \sum_{i = 2}^{r + s} \nu_i \tilde{\mu}_i(T, ~ P) \right\} \Bigg] \end{align*} \]
平衡定数を理論的に求めるには上記最右辺を利用しましょう。一方、相乗 \(\prod\) による記述を利用すれば実験的に平衡定数を決定することが可能です。
平衡定数を理論的に算出する
化学便覧や物理化学書の巻末には、様々な化学種について標準モルギブス自由エネルギーの物性値が記載されています。
それを利用して例えば、ヨウ化水素の生成反応を例に平衡定数を求めてみましょう。
\[ \text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftarrows 2\text{HI} \]
標準圧力 \(P^\circ = 1 ~ [\text{bar}]\) の下、\(25 ~ [\text{℃}]\) における標準モルギブス自由エネルギーは下記の通り。
| \(\text{H}_2\) | \(\text{I}_2\) | \(\text{HI}\) | |
|---|---|---|---|
| \(\bar{G}^\circ_i ~ [\text{kJ/mol}]\) | 0 | 0 | 1.56 |
上記の物性値から
\[ \begin{align*} K_P &= \exp \bigg[ -\frac{1}{RT} \sum_{i = 1}^{r + s} \nu_i \bar{G}^\circ_i \bigg] \\[15pt] &= \exp \bigg[ -\frac{1}{8.31451 ~ [\text{J/K・mol}] \cdot 298.15 ~ [\text{K}]} \big( -1 \cdot 0 ~ [\text{kJ/mol}] - 1 \cdot 0 ~ [\text{kJ/mol}] + 2 \cdot 1.56 ~ [\text{kJ/mol}] \big) \bigg] \\[15pt] &= 0.284 \end{align*} \]
このように平衡定数を理論的に求めることが可能です。
平衡定数を実験的に求める
実験的に平衡定数を求めるには、平衡状態にある系について各成分の分圧あるいは濃度の測定値が必要です。
測定後に…
\[ \begin{align*} K_P &= \prod_{i = 1}^{r + s} \left( \frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} \\[15pt] &= \frac{\displaystyle\left( \frac{P_\text{HI}}{P^\circ} \right)^2}{\displaystyle \left( \frac{P_{\text{H}_2}}{P^\circ} \right) \left( \frac{P_{\text{I}_2}}{P^\circ} \right)} = \frac{P_\text{HI}^2}{P_{\text{H}_2} P_{\text{I}_2}} \end{align*} \]
にそれぞれ値を代入すれば平衡定数が算出されます。
前項のように物性値から理論的に計算できれば実験をする必要がありませんが、化学便覧などに掲載されていない化学種の場合は実験的に決めざるを得ません。
加えて化学反応は事実複雑であり平衡定数は実験的に求めるのが主流です。
ヨウ化水素の生成反応を例にしたとき、上記の計算で示されるようにちょうど \(P^\circ\) は分母分子で打ち消されましたが、反応の種類によっては打ち消されることなく残ってしまうことがあります。
例えば、次のアンモニア生成反応について考えると
\[ 3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightleftarrows 2\text{NH}_3 \]
平衡定数は次のようになります。
\[ K_P = \frac{\displaystyle \left( \frac{P_{\text{NH}_3}}{P^\circ} \right)^2}{\displaystyle \left( \frac{P_{\text{H}_2}}{P^\circ} \right)^3 \cdot \frac{P_{\text{N}_2}}{P^\circ}} = \frac{ P_{\text{NH}_3}^2 P^{\circ 2}}{P_{\text{H}_2}^3 P_{\text{N}_2}} \]
標準圧力 \(P^\circ\) は式中に残ってはいますが、平衡定数が無次元であることを考慮すると必然的に上記の記述となります。
しかし、通常 標準圧力は \(P^\circ = 1 ~ [\text{bar}]\) にとるので、平衡定数の値には影響は及びません。
また標準状態における濃度は \(C^\circ = 1 ~ [\text{mol/L}]\) にとります。
要するに、単純に系に含まれる分圧または濃度を測定するのみで良いということになりますが、次元 ( 単位 ) は注意する必要があります。特に圧力では \([\text{bar}]\) を用いています。