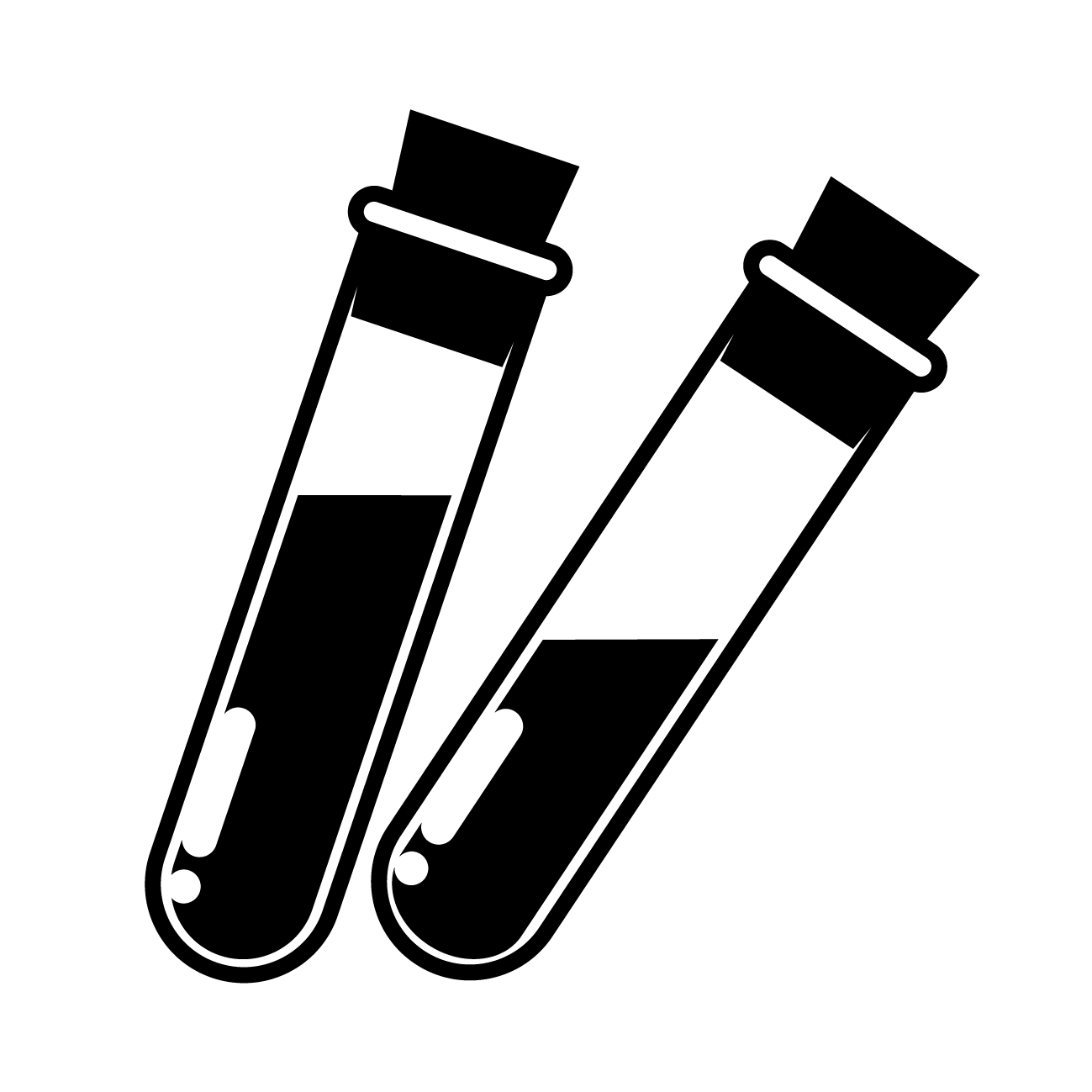熱力学では系の状態を知るために外から刺激を加えてその応答を測定するやり方が行われます。
刺激とはつまり仕事のことであり、等温操作と断熱操作によって系を操作したときに系がどんな反応を示すかを整理します。
当ページでは理想気体に限定し、等温操作・断熱操作を行ったときの挙動と、操作の途中で生じる仕事や熱について説明します。
また断熱過程において成立するポアソンの関係式の導出も見ていきましょう。
■目次■
等温操作
等温操作による理想気体の状態変化
温度一定の条件で理想気体の体積を変化させた場合の挙動を考えます。
改めて「挙動」とは何かというと、理想気体がどの様な平衡状態を取り得るかを指します。
もう少し分かりやすく言うと、理想気体の体積を \(V\) に設定したとき、温度 \(T\) や圧力 \(P\) がどの様な値を取るかを調べることです。
次に示すのは理想気体が封入されたピストン付きのシリンダー。ピストンを操作することで自在に体積を操作できます。
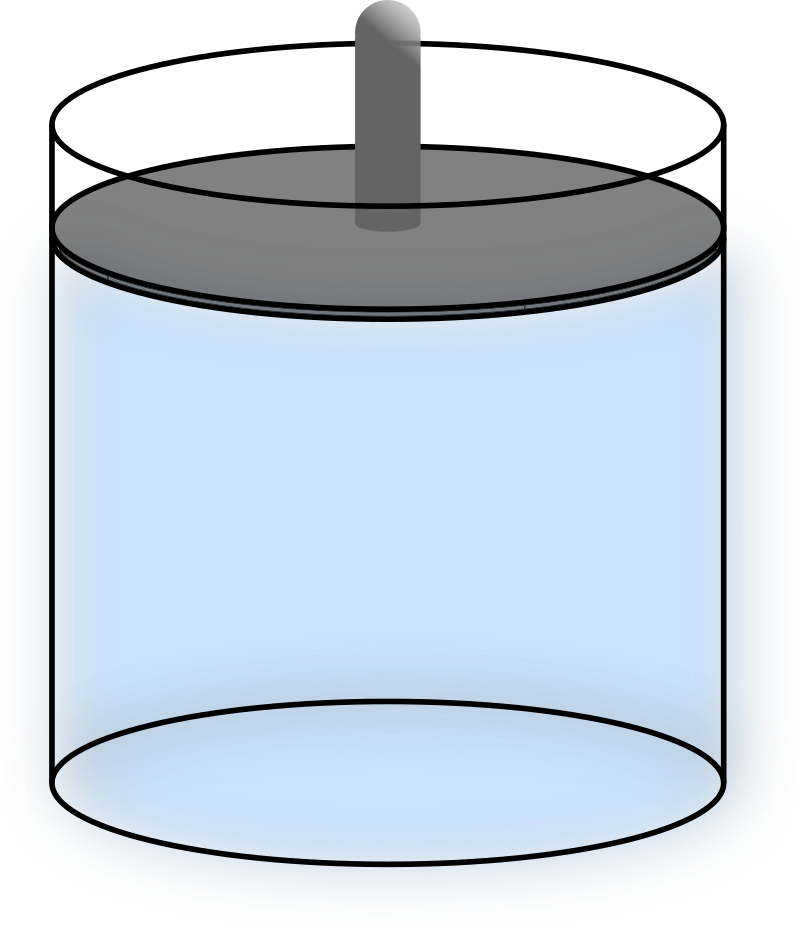
等温過程の場合、理想気体の状態方程式(1)から直ちに圧力、体積、温度がどの様に対応しているかはすぐに分かります。
\[ PV = nRT \]
ここで \(n\) は物質量、\(R\) は気体定数です。
また式(1)をグラフ化すれば、系が体積変化するときの様子が視覚的に分かりやすくなります。


1つ目は \(T\)-\(V\) グラフで体積変化に伴う温度の挙動を、2つ目は \(P\)-\(V\) グラフで体積変化に伴う圧力の挙動を示しています。
ただし注意しなければならないのは、それぞれのグラフは準静的操作によって体積を \(V_0\) から \(V\) へ変化させた場合を表していることです。
準静的操作でなければ理想気体は操作途中に非平衡状態となり複雑な運動をしてしまうので、正しい圧力や温度を測定できません ( 熱力学的に圧力や温度を定義できません ) 。
すると上記の様に系がたどる状態を曲線として表すことができないのです。
※操作前後の平衡状態は状態図上に点として表現されます。状態図に曲線が描かれる場合は暗に準静的操作によって変化させている事を表しています。準静的ではない場合は、操作前後の2状態のみがグラフ上に定義されます。
上記の準静的操作を記号で表現すれば式(2)の通り。
\[ (T; ~ V_0, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{iq}} ~ (T; ~ V, ~ n) \]
左辺と右辺はそれぞれ操作前後の平衡状態を表しています。また矢印の上についた「iq」は、等温準静的を意味する quasi-static isothermal の頭文字から来ています。
ではもう一度グラフを見てもらいましょう。\(T\)-\(V\) グラフでは温度が一定であるため直線状になっていることが分かります。
ただこれは何も等温操作だからではありません。一般に気体に少しでも力を加えると温度はすぐに変化してしまうことを思い出しましょう。
しかし今は準静的に静かに操作する状況を考えています。
多少の温度変化があったとしても環境との熱のやり取りの方が早ければ温度は一定に保たれるということです。余談かもしれませんが重要ですよ。
一方で \(P\)-\(V\) グラフは、反比例する曲線となります。
準静的操作によって理想気体の温度が一定に保たれるので、式(1)の右辺も定数となり圧力と体積が \(PV = \text{Const.}\) の関係で表されることから理解できます。
理想気体がする等温最大仕事
状態方程式(1)からは、系の圧力、体積、温度の関係を記述することができました。
さらに仕事やエネルギーの観点から状態の記述を考えることによって、気体が持つ性能を評価できるようになります。
ではさっそく理想気体が等温過程でする仕事を考えていきますが、注意点が2つあります。
1つ目は、何度も述べているように今考えているのは準静的過程における仕事であることで、そのときにする仕事を最大仕事 \(W_{\text{max}}\) と言います。
最大仕事は数学的に求めることが可能ですが、非平衡状態を経由した場合にする仕事 \(W\) は数学的な表現が困難です。
ただし仕事と最大仕事は最大仕事の原理に従って \(W \leq W_{\text{max}}\) という関係を利用することは可能です。
続いて注意点2つ目は、先に示したグラフから分かりますが等温操作では理想気体の圧力が一定値を取らないことです。
気体がする仕事は圧力と体積変化の積 \(P \Delta V\) によって表すことができましたが、これは圧力が一定の場合でしか適用できません。
これを解決するには積分を利用します。
仮に圧力が一定の状態を考えれば、\(P\)-\(V\) グラフは直線状となりますが、その間に系がする仕事はグラフと \(V\) 軸に挟まれた領域の面積に等しくなります。

同様に考えれば、いま求めたい等温最大仕事は \(PV\) 曲線と \(V\) 軸に挟まれる領域の面積を計算すれば良いことが分かります。

\[ W_{\text{max}}(T; ~ V_0 \rightarrow V) = \int_{V_0}^{V} PdV \]
数学的意味は上記のとおりですが、物理的には準静的操作のその時々における微小仕事 \(\delta W = PdV\) をたくさん足し合わせたもの \(\int \delta W\) と理解できます。
そして上記の内容から式(3)に理想気体の状態方程式(1)を代入して計算を実行すれば次式が導けます。
\[ \begin{align*} W_{\text{max}}(T; ~ V_0 \rightarrow V) &= \int_{V_0}^{V} PdV \\[15pt] &= \int_{V_0}^{V} \frac{nRT}{V}dV \\[15pt] &= nRT \ln \frac{V}{V_0} \end{align*} \]
理想気体の最大吸熱量
等温操作では、系と外部環境との間で熱のやり取りをすることができます。
系が準静的に変化するときに吸収する熱量は最大値をとり、それを最大吸熱量 \(Q_{\text{max}}\) と呼びます。
熱を直接計算によって求めるのは実際に難しいのですが、次式で示す熱力学第一法則を用いれば間接的ですが求めやすくなります。
\[ \Delta U = -W + Q \]
\(\Delta U\) は系が持つ総エネルギーを表す内部エネルギー、\(W\) は系が外界にする仕事、\(Q\) は系が外部環境から吸収する熱を表しています。
準静的過程においては、式(5)の仕事と熱をそれぞれ最大仕事と最大吸熱量に置き換えれば良いので、結局最大級熱量は次式で表現できることになります。
\[ \begin{align*} Q_{\text{max}}(T; ~ V_0 \rightarrow V) &= \Delta U + W_{\text{max}}(T; ~ V_0 \rightarrow V) \\[15pt] &= \Delta U + nRT \ln \frac{V}{V_0} \end{align*} \]
式(6)によって理想気体が準静的に変化するときの最大吸熱量を定式化できました。
しかし理想気体の性質から、もう少し簡単な表式にすることが可能です。
それには理想気体では体積変化にともなう内部エネルギー変化が理想的に 0 であるとしたことを利用します。
\[ \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, ~ n} = 0 \]
式(7)が意味することは、要するに理想気体の内部エネルギーは温度のみに依存するという事です。
\[ \begin{align*} dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V, ~ n} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, ~ n} dV \\[20pt] \rightarrow ~ dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V, ~ n} dT \\[20pt] dU &= C_{V} dT \end{align*} \]
\(\frac{\partial U}{\partial T}\) は定積熱容量 \(C_{V}\) に置き換えています。
定積熱容量は一般に温度に依存するので、式(8)から内部エネルギー変化 \(\Delta U\) を求めるには積分が必要となるのですが…
様々な気体で定積熱容量を計測すると、広い温度範囲で一定値をとることが知られています。
そこでこの事実を理想化して、理想気体では定積熱容量が定数であると考えます。
したがって、理想気体の内部エネルギー変化は温度変化のみで決まるという単純な関係に整理されます。
\[ \Delta U = C_{V} \Delta T \]
ただ、今考えている等温操作では温度が常に一定であるため \(\Delta T = 0\) となり、結局内部エネルギー変化も \(\Delta U = 0\) となるのです。
つまり理想気体を等温準静的操作によって変化させたときの最大吸熱量は式(10)で表現されることになります。
\[ Q_{\text{max}}(T; ~ V_0 \rightarrow V) = nRT \ln \frac{V}{V_0} \]
式(4)と式(10)を見比べれば、等温最大仕事と最大吸熱量の大きさが共に等しいことが分かるでしょう。
要するに理想気体においては、仕事をした分だけ環境から熱を吸収するし、逆に仕事をすればその分だけ環境に熱を逃がすという仕組みになっているのです。
理想気体の等温操作を表す式
理想気体では等温最大仕事と最大吸熱量が等しくなることを説明してきましたが、準静的操作以外の場合でも仕事と熱は等しい値を取ります。
つまり理想気体を等温操作によって変化させたとしても内部エネルギー変化は 0 という事です。
なぜなら理想気体の内部エネルギー変化を式(9)で与えたように、温度変化のみに依存することに起因します。
内部エネルギーは状態量なので、操作前後の平衡状態が分かれば一意に定まります。
これは操作の途中で理想気体がどの様な変化をたどってきたかは一切関係がないことを意味します。
そして等温操作では操作前後の温度は必ず等しくなるので、温度変化は 0 です。
したがって式(9)から内部エネルギー変化も 0 となります。
再度まとめれば、理想気体について等温操作をしたときの仕事とエネルギーの関係は一般に式(11)で記述することができるということになります。
\[ W = Q \]
断熱操作
断熱操作による理想気体の状態変化
理想気体における等温操作の説明で見てきたように、まずは断熱準静的操作によって理想気体がどの様な挙動を示すのかを明らかにしておきましょう。
結論から言えば、断熱過程における理想気体の圧力、体積、温度の関係は次式で表現されます。
\[ TV^{\gamma - 1} = \text{Const.} ~~~ \text{or} ~~~ PV^\gamma = \text{Const.} ~~~ \left(~ \gamma = \frac{\bar{C}_V + R}{\bar{C}_V} ~\right) \]
式(12)はポアソンの関係式と呼ばれます。
また式中に現れる \(\bar{C}_V\) は 1 \([\text{mol}]\) あたりの定積熱容量です ( つまり \(\frac{C_V}{n}\) ) 。
実際に式(12)それぞれをグラフ上に表現したものが次の図。


グラフを見れば分かる通り、断熱操作では体積の変化に伴って理想気体の温度も圧力も変化しています。
では結果はここまでとして、このポアソンの関係式(12)は本当に正しいのか、どの様に導かれるのかを次の項で理論的に示すこととします。
ポアソンの関係式
ポアソンの関係式(12)は断熱過程を記述する式ですが、理想気体の状態方程式のみから導くことはできません。
なぜなら状態方程式(1)の中には熱を表す量が一切含まれていないからです。
\[ PV = nRT \]
「温度は熱と関係があるのではないか?」と思われるかもしれませんが、これらは全く別の物理量であることに注意です。
実際に熱とは温度差 \(\Delta T\) があって初めて生じるものでしたね。
では、ポアソンの関係式を導くにはどうすれば良いでしょうか。
熱と関係がある法則は上記でも既に出てきている熱力学第一法則がありました。これを利用していきましょう!
次に示すのは準静的過程において成立する熱力学第一法則から熱を消去した式です。
\[ \begin{align*} \Delta U &= -W_{\text{max}} \\[15pt] dU &= - \delta W \end{align*} \]
ここで次の断熱操作を考えます。
\[ (T_0; ~ V_0, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{aq}} ~ (T; ~ V, ~ n) \]
式(14)について矢印の上についた「aq」は、断熱準静的を意味する quasi-static adiabatic の頭文字から来ています。
また断熱操作では体積の変化に伴って温度も変化することに注意して下さい。上記で示したグラフでも実際に温度は変化していましたよね。
これから考えるべきことは式(13)をどうにかして圧力、体積、温度だけで表現することです。
理想気体の内部エネルギー変化は式(8) \(dU = C_V dT\) で置き換えることができます。
また仕事 \(\delta W\) はこれまでと同様に圧力と体積変化の積 \(PdV\) を使いましょう。
\[ C_V dT = - P dV \]
式(15)に理想気体の状態方程式(1)を代入すれば式(16)のようになります。
\[ C_V dT = - \frac{nRT}{V} dV \]
さて、いま考えている断熱変化では何度も言うように体積の変化に伴って温度も変化します。つまり実際は \(T = T(V)\) とでも書いておくべきなのです…。
そのため式(16)をそのまま両辺を積分しようとしても、\(T(V)\) の具体的な表式が分からないので計算ができません。
このような場合、変数分離型の微分方程式の解法を利用して計算を進めることができます。
左辺には温度、右辺には体積に関する量をまとめて
\[ C_V \frac{dT}{T} = - nR \frac{dV}{V} \]
これなら両辺積分を実行できます。
積分範囲は \(V_0 \rightarrow V\) のとき \(T_0 \rightarrow T\) であることに注意して
\[ \begin{align*} C_V \int_{T_0}^{T} \frac{dT}{T} = - nR \int_{V_0}^{V} \frac{dV}{V} \\[15pt] \therefore ~ C_V \ln \frac{T}{T_0} = -nR \ln \frac{V}{V_0} \end{align*} \]
さてここからもう少し式変形を行えば、ポアソンの関係式にたどり着くことができます。
指数対数の性質を利用して
\[ \begin{align*} \ln \frac{T}{T_0} = \ln \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{nR}{C_V}} \\[15pt] \Leftrightarrow ~ TV^{\frac{nR}{C_V}} = T_0V_0^{\frac{nR}{C_V}} \end{align*} \]
ここで \(\bar{C}_V = \frac{C_V}{n}\) および \(\gamma = \frac{\bar{C}_V + R}{\bar{C}_V}\) と置けば、
\[ TV^{\gamma - 1} = T_0{V_0}^{\gamma - 1} = \text{Const.} \]
となります。
両辺を見るとそれぞれ形式が全く同様なので、初期状態を表す \(T_0{V_0}^{\gamma - 1}\) を定数としてあげればポアソンの関係式(12)が導けたことになります。
更に理想気体の状態方程式を利用して式(20)から温度を消去すれば、圧力と体積の表式も得られます。
\[ \begin{align*} TV^{\gamma - 1} &= \frac{PV}{nR}V^{\gamma - 1} = \text{Const.} \\[15pt] \Leftrightarrow ~ PV^{\gamma} &= \text{Const.} \end{align*} \]
式変形の途中で現れた \(nR\) は定数部分に吸収させています。
理想気体が断熱過程でする最大仕事
理想気体が断熱過程でする仕事を見ておきましょう。
と言っても実は非常に簡単で、なぜなら断熱過程では式(13)で示すように系がする仕事は内部エネルギー変化に等しいからです。
内部エネルギーは式(8)によって操作前後の温度差のみで決まるので、すなわち理想気体がする断熱仕事 \(W_{\text{ad}}\) は
\[ - W_{\text{ad}} = C_V(T - T_0) \]
で与えられることが分かります。
ところで、式(22)は準静的であるか否かに関わらず常にこの表式によって与えられます。
それは内部エネルギーが状態量であるため、操作前後の平衡状態のみが重要であって、操作途中の状態には全く依存しない性質ゆえです。
しかし等温最大仕事で積分を用いて計算したように、断熱操作における最大仕事を計算することももちろん可能です。
実際に計算を行ってみましょう。
まず前提として、理想気体の温度と体積が初期状態 \((T_0; ~ V_0)\) であるときの圧力を \(P_0\) としておきます。
つまり理想気体の状態方程式(1)から \(P_0 V_0 = nRT_0\) の関係が成立しています。
そして同時にポアソンの関係式(12)から \(PV^{\gamma} = P_0{V_0}^{\gamma}\) も成立しています。
これらの式に留意して微小仕事の積分を実行すれば
\[ \begin{align*} \int_{V_0}^{V} PdV &= \int_{V_0}^{V} P_0\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma} dV \\[15pt] &= P_0 {V_0}^{\gamma} \int_{V_0}^{V} \frac{dV}{V^{\gamma}} \\[15pt] &= P_0 {V_0}^{\gamma} \biggl[\frac{1}{1 - \gamma} V^{1 - \gamma}\biggr]_{V_0}^{V} \\[15pt] &= \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{1 - \gamma} (V^{1 - \gamma} - {V_0}^{1 - \gamma}) \end{align*} \]
が得られます。
もう少し整理してみましょう。
今度は温度と体積に関するポアソンの関係式 \(TV^{\gamma - 1} = T_0{V_0}^{\gamma -1}\) が成立していることを利用します。
\[ \begin{align*} \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{1 - \gamma} (V^{1 - \gamma} - {V_0}^{1 - \gamma}) &= \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{1 - \gamma} {V_0}^{1 - \gamma} \left\{\left(\frac{V}{V_0}\right)^{1 - \gamma} - 1\right\} \\[15pt] &= \frac{P_0 V_0}{\gamma - 1} \left\{1 - \left(\frac{V}{V_0}\right)^{1 - \gamma}\right\} \\[15pt] &= \frac{nRT_0}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{T}{T_0}\right) \end{align*} \]
更に…
\[ \begin{align*} \frac{nRT_0}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{T}{T_0}\right) &= \frac{nRT_0}{\gamma - 1} \cdot \frac{T_0 - T}{T_0} \\[15pt] &= \frac{nR(T_0 - T)}{\gamma - 1} \end{align*} \]
\(\gamma = \frac{\bar{C}_V + R}{\bar{C}_V}\) だったことを利用して、
\[ \begin{align*} \frac{nR(T_0 - T)}{\gamma - 1} &= \frac{nR(T_0 - T)}{R / \bar{C}_V} \\[15pt] &= n\bar{C}_V (T_0 - T) \\[15pt] &= C_V (T_0 - T) ~~~ \left(~ \because ~ \bar{C_V} = \frac{C_V}{n} ~\right) \end{align*} \]
となって、断熱過程における最大仕事の表式をいくつか与えつつ、計算結果は式(22)と同じ関係すなわち内部エネルギー変化に戻ることから式(23)の正当性も確かめられるでしょう。
等温線と断熱線
理想気体が等温環境下あるいは断熱条件下において準静的過程を経由するときの \(P\)-\(V\) 曲線が次式で表されることを前節までに見てきました。
\[ \begin{align*} \text{Isothermal :} ~ & PV = \text{Const.} \\[15pt] \text{Adiabatic :} ~ & PV^{\gamma} = \text{Const.} \end{align*} \]
それぞれの関係式について、右辺の定数値は系を操作する前の初期状態によって様々な値を取ります。
実際に定数値を変化させたときに得られる曲線群が次に示す図です。


等温操作によって実現される曲線を等温線、他方断熱操作によって実現される曲線を断熱線と言います。
それぞれのグラフを比較すると、どちらも非常に似ているように見えますが、これらを重ねてみるとその違いが分かりやすくなります。

赤色の曲線は等温線、青色の曲線が断熱線を表しています。
図を見てみると分かりますが、等温線と断熱線は様々な点で交差しています。また特徴としては断熱線の方がグラフの傾きが急であること。
よく確認するために一部分を抽出して拡大してみましょう。

等温線は気体の状態方程式 \(PV = nRT\) に等しいので、下側の曲線ほど温度が低い状況を表しています。
一方、断熱操作は何度も言うように体積の変化に伴って温度も変化しますが、そのことがグラフにもしっかりと現れています。
実際に断熱線を見れば、温度の異なる等温線と交わっており体積によって温度が異なる事を示しています。
断熱操作では体積が増加したとき温度は下がることが理解できますが、これは気体が断熱膨張したときに温度が下がることを思い出せば納得できるでしょう。
まとめ
理想気体について等温操作、断熱操作を準静的に行ったときの圧力、体積、温度の関係は次式で表現されます。
\[ PV = \text{Const.} \]
\[ PV^{\gamma} = \text{Const.} \]
【サイト運営 : だいご】
今年で物理化学歴13年目になります。
大学入試2次数学でたった3割しか得点できなかったいわゆる数弱落ちこぼれ。それでも好きこそものの上手なれと言ったところか、学会で最優秀賞受賞したり首席卒業できてしまったので、役に立つ知識を当サイトに全て惜しみなく公開しようと思います。ブックマークをオススメ。