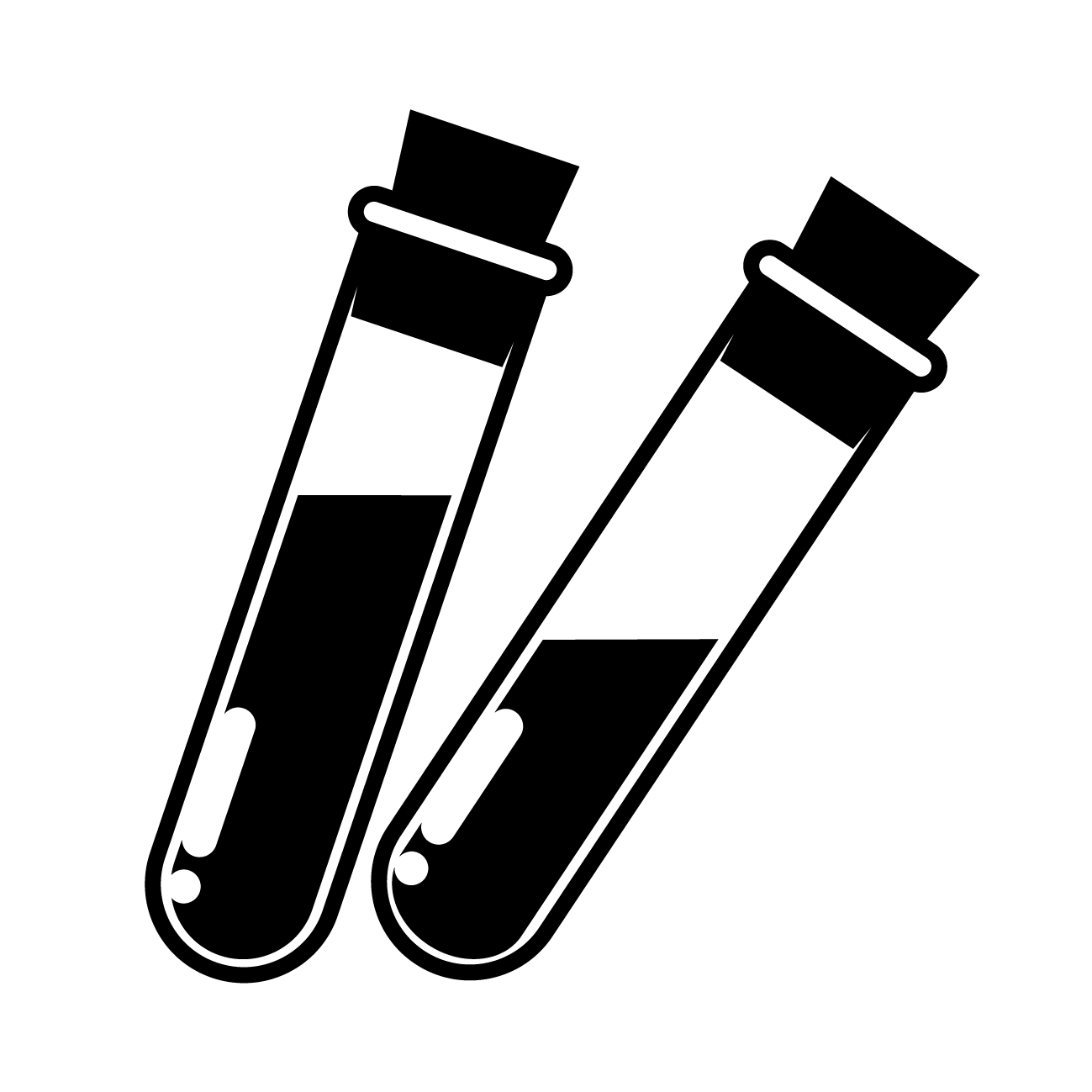当ページの内容は以下のコンテンツの続編ともなっているので、ぜひ御覧ください。
※酸塩基平衡について詳細は
こちらから
さて、上記コンテンツでは水を溶媒として酸や塩基を溶解させた際に生じる酸塩基反応を解説しています。
そこでも取り上げていますが、その反応式とは次に示す通りのものです。
式(1)
\[
\text{HA} + \text{B} ~ \rightleftharpoons ~ \text{A}^- + \text{HB}^+
\]
この反応式を見ると水は一見反応に関与していないように見えますが、実際はその逆なのです。
水の性質を上手く利用することによって得られる情報があることを以下で見ていきましょう。
水のイオン積
水と聞くと、「無害である」とか「中性的である」といったイメージを持たれるかもしれません。
そんな水ですが、科学的に見ると様々な性質を持ち合わせています。
例えば、当コンテンツで重要になる電気的性質ですが、水はしばしば電気を通すと言われますね。
その原因として考えられるのは、水に含まれる不純物です。
例えば、水道水では塩素系の化合物が含まれていたり、蛇口から出てくるまでに水道管から金属イオンが溶け出しているなど考えられる原因はたくさんあります。
しかし面白いは高度に蒸留して不純物を完全に取り除いた蒸留水を用いた実験で、電極を差し込んだときになんと微弱な電流が流れるという事実です。
つまり、水に含まれる不純物が電気伝導を示していたという考え以前に、水自体がそもそも電離しているのでは? と考えざるを得ないのです。
式(2)
\[
\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-
\]
水と水が相互に反応しあった結果、オキソニウムイオンと水酸化物イオンに電離するという反応です。
ただし先程「電極を差し込むと微弱な電流が流れた」と言ったように、この平衡反応が大きく生成物側に偏っているのではありません。
もし水が好き放題イオン化していたら恐らく私達にとって害を及ぼす存在となっていたでしょう。
話を戻しますが、反応式(2)で示したような同じ分子内で起こる水素イオン移動反応を
自己プロトリシスと言います。
ではこの水の自己プロトリシスの場合、どのくらい平衡が右側に偏っているのかは非常に興味深い問題です。
実際に測定された平衡定数が次になります。
式(3)
\[
K_{\text{w}} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} ~~~ (~ 25 \text{ ℃} ~)
\]
式(3)で示したような、平衡定数を
自己プロトリシス定数と言い、また水の場合では
水のイオン積と言います。
溶媒である水の濃度 \([\text{H}_2\text{O}]\) はキャンセルされるので、非常に簡素な表式となります。
そして実際に得られる測定値は極々小さい値であることも分かるでしょう。
また式(3)には温度を条件として記載しています。もし温度が高ければ一般に電離しやすくなるために、このイオン積の値は大きくなっていきます。
とは言え、それでも非常に小さな値であることには変わりありません。
このように大した存在に見えないのにも関わらず一体何の役に立つのかと思われるかもしれません。
しかしこれから導かれる結果は、酸性物質と塩基性物質という相反する物質を統一的に理解するための手段を提供してくれるのです。
酸と共役塩基 ( 塩基と共役酸 ) の関係
まずは、酸 \(\text{HA}\) と共役酸 \(\text{A}^-\) の間にある関係を導きます。
酸 \(\text{HA}\) を水に溶解させたときの平衡反応は以下のとおりです。
式(4)
\[
\text{HA} + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+
\]
酸解離定数は次式で表されます。
式(5)
\[
K_{a(\text{HA})} = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}
\]
ここでとても神経質な方は恐らく居ても立っても居られないかもしれませんが…
式(4)で示した平衡反応は、生成した共役塩基や共役酸どうしが再度反応しあってもとに戻ることを表していますよね。
しかしよく考えてみると共役塩基や共役酸の周囲には溶媒である水が豊富にあるはずで、これらとの反応は考慮しなくてもよいのでしょうか?
実際に共役塩基 \(\text{A}^-\) の水との反応を考えると次のようになります。
式(6)
\[
\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{HA} + \text{OH}^-
\]
そして反応式(6)における塩基解離定数が次式で表されるのは問題ないですよね。
式(7)
\[
K_{b(\text{A}^-)} = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}
\]
そしてここからなのですが、いま反応式(4)および(6)で表された平衡反応は1つの系で同時で起きています。
そのためそれらの平衡状態を記述する平衡定数、すなわち式(5)および式(7)に含まれる \([\text{HA}]\) は両方同じ値をとっているはずです。
加えて \([\text{A}^-]\) も同様に同じ値を取ります。
つまり、式(5)と式(7)から次式が成立します。
式(8)
\[
\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{K_{a(\text{HA})}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{[\text{OH}^-]}{K_{b(\text{A}^-)}} \\[15pt]
\Leftrightarrow ~ K_{a(\text{HA})} K_{b(\text{A}^-)} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]
\]
そしたら何と、オキソニウムイオンと水酸化物イオンの濃度の積に整理されるのです。
お気づきかと思いますが、そうです前節で紹介した水のイオン積 \(K_{\text{w}}\) と同じ格好をしていますよね。
しかしこのまま式(8)が \(K_{\text{w}}\) と等しいとしても良いのでしょうか。
違和感を感じられた方は、センスがあるかもしれません。
そもそも水のイオン積は水だけの状態で定義しました。
ところが式(8)は水にある酸を添加して場合の状態を考えており、この2つの状況は全く異なることに気が付きはしないでしょうか。
さて、焦らしても仕方がないので結論を述べますが、実は
希薄条件下であるなら常に成立すると考えて問題ないのです。
添加する酸が希薄であるため、周囲の水の自己解離にそれほど影響を及ぼさないということです。
逆に高濃度条件の下では、イオン化が抑制されてしまうためイオン積は大きくずれることになります。
※高濃度条件に関する理論は、デバイ・ヒュッケル理論があります。
以上まとめると、結局式(8)は水のイオン積と等しいと置くことができ、次式が成立することになります。
式(9)
\[
K_{a(\text{HA})} K_{b(\text{A}^-)} = K_{\text{w}} = 1.0 \times 10^{-14}
\]
すると、酸とその共役塩基の解離定数が1対1で結ばれることが分かるでしょう。
これはつまり塩基性物質であったとしても、塩基解離定数を用いずに酸解離定数を用いて表現できることを意味します。
そのためわざわざ塩基解離定数を利用しなくても良いことになります。
更に、全ての物質について酸解離定数のみで表現できるので、数値の大小比較をするだけで酸として働くのか、塩基として働くのかをより簡潔に表現できるようになるのです。
式(9)を常用対数で表せば更に使い勝手が良くなります。
式(10)
\[
\text{p}K_{a(\text{HA})} + \text{p}K_{b(\text{A}^-)} = 14 ~~~ (~ 25 \text{℃} ~)
\]
ここまでの内容を今度は塩基と共役酸について考えても、同様に以下の関係式が導かれるので確認してみて下さい。
式(11)
\[
\text{p}K_{a(\text{HB}^+)} + \text{p}K_{b(\text{B})} = 14 ~~~ (~ 25 \text{℃} ~)
\]
例えば式(11)を利用すれば、こちらのコンテンツで取り上げたアンモニウムイオン \(\text{NH}_4^+\) の酸解離定数を求めることができます。
アンモニア水溶液を調製し、ここから塩基解離定数を測定します。
アンモニアの塩基解離定数
\[
K_b = 1.8 \times 10^{-5}
\]
そして式(11)からアンモニウムイオンの酸解離定数を計算すると \(\text{p}K_{a(\text{HB}^+)} = 9.25\) を得ることができます。
ただ、この例では式(11)を利用しましたが、式(10)も式(11)も本質的に全く同じことを表しているので覚える必要はありません。
なぜなら内容の所々で現れる、共役酸や共役塩基は「共役」という形容詞がつくものの、結局は酸および塩基なので、
式(11) の 塩基 \(\text{B}\) を 塩基 \(\text{A}^-\) に置き換えれば、それは式(10)を言っているに過ぎないからです。
重要なのは式(10)や式(11)が何を示しているかであり、それが題目にもある「酸とその共役塩基との間の関係」もしくは「塩基とその共役酸との間の関係」です。
これら2つを更に一般化して説明すれば、ある酸の酸解離定数と、その物質が水素イオンを失った状態における塩基解離定数との関係ということになります。
強酸と強塩基
水の性質を利用することによって、酸塩基解離定数に関する知見を得ることができました。
式(10)や式(11)を利用すれば、間接的に \(\text{p}K_a\) や \(\text{p}K_b\) を求められるので非常に便利です。
ここからは少し色が変わって、一般的に強酸や強塩基と呼ばれる物質の話をしていきます。
これらは
更に、
ところが良いことばかりではありません。
例えば強酸および強塩基と呼ばれる物質群の解離定数を求めようとしても不可能なのです。
それはなぜか、以下で順を追って解説していきます。
強酸・強塩基
まず強酸および強塩基とは一体何者かを知る必要があります。
酸塩基反応は一般に平衡反応となりますが、強酸あるいは強塩基を水に溶解させたときにはその限りではなく、次の反応式のように平衡が生成物側にほぼ完全に偏ってしまいます。
式(12)
\[
\text{HA} + \text{H}_2\text{O} ~ \rightarrow ~ \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \\[15pt]
\text{B} + \text{H}_2\text{O} ~ \rightarrow ~ \text{HB}^+ + \text{OH}^- \\[15pt]
\]
つまり添加した酸や塩基のほぼ全ての分子が解離し、電離度が \(\alpha \simeq 1\) の状態となるのです。
これは、添加した酸の強度がオキソニウムイオンのそれよりも非常に強いためです。
つまり強酸 \(\text{HA}\) は酸の強度が非常に強く一方的に ( 周囲の水に ) 水素イオン供給をするため、
結果生成するオキソニウムイオンは水素イオンを \(\text{A}^-\) にお返ししようと思ってもさせて貰えないという状況になるのです。
また強塩基は酸とは真逆で一方的に ( 周囲の水から ) 水素イオンを強奪します。
結果生成する水酸化物イオンは水素イオンを取り返そうとするものの強塩基には逆らえないのです。
内部事情を話していくと概ねこの様な感じになりますが、端的に言い表せば強酸・強塩基とは水に溶解させることによってほぼ完全に電離する物質のことを指すワケです。
強酸と強塩基の \(\text{p}K_a\)
ここで酸あるいは塩基の電離度はその濃度が低いほど上昇するという性質を持つため、物質固有の値として定めるのは少々難があったことを思い出していただきましょう。
そのため一般に酸や塩基の強度を指標としては前述で示した酸解離定数 \(\text{p}K_a\) を利用するのが都合が良いのでした。
しかし、強酸や強塩基では電離度がほぼ1に近いため、オストワルドの希釈律を利用した酸解離定数の決定は不可能です。
式(13)
\[
K_a = \frac{C \alpha^2}{1 - \alpha} \rightarrow \infty ~~~ (~ \alpha \rightarrow 1 ~)
\]
そこで定数を直接求めるのはとりあえず先回しにして、強酸や強塩基の酸解離定数が一体どのような値の範囲をとり得るのかだけでも知っておきましょう。
糸口となるのは、前項で示したオキソニウムイオンと水酸化物イオンの酸解離定数です。
これらは以下に示す方法で求めることができます。まずはオキソニウムイオンから。
式(14)
\[
\text{H}_3\text{O}^+ + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+
\]
式(14)からオキソニウムイオンの酸解離定数は次式で与えられます。
式(15)
\[
K_{a (\text{H}_3\text{O}^+)} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 1 \\[15pt]
\therefore ~ \text{p}K_{a (\text{H}_3\text{O}^+)} = 0
\]
なるほど、\(\text{p}K_a\) は小さいほど強い酸性を示すのであったから、強酸のそれは0よりも小さくなければなりません。
式(16)
\[
\text{p}K_a < 0 ~ \Leftrightarrow ~ K_a > 1
\]
逆に水酸化物イオンから得られる塩基解離定数も同様に考えれば次式が得られます。
式(17)
\[
\text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-
\]
式(18)
\[
K_{b (\text{OH}^-)} = \frac{[\text{OH}^-]}{[\text{OH}^-]} = 1 \\[15pt]
\therefore ~ \text{p}K_{b (\text{OH}^-)} = 0
\]
塩基の場合も \(\text{p}K_b\) は小さいほど強い塩基性を示すので、強塩基とは少なくとも次式を満たす必要があります。
式(19)
\[
\text{p}K_b < 0 ~ \Leftrightarrow ~ K_b > 1
\]
更に前節でも示しましたが、\(\text{p}K_b\) は \(\text{p}K_a\) に置き換えることができるので式(10)あるいは式(11)の関係式を用いると
式(20)
\[
14 - \text{p}K_a < 0 \\[15pt]
\therefore ~ \text{p}K_a > 14
\]
この様になります。
以上まとめると次の通りです。
式(21)
\[
\begin{align*}
&\text{p}K_a < 0 && \text{( Strong acid )} \\[15pt]
&\text{p}K_a > 14 && \text{( Strong base )} \\[15pt]
\end{align*}
\]
補足的な説明にはなってしまいますが、式(21)とは逆に \(\text{p}K_a\) が0から14の間であるものを弱酸・弱塩基ということにしましょう。
式(22)
\[
0 < ~ \text{p}K_a < 14 ~~~ \text{( Weak acid and base )}
\]
水平化効果
水平化効果
前項では強酸と強塩基を水に溶解させたときに完全に電離する、すなわち電離度がほぼ1となるためにオストワルドの希釈律が利用できず \(\text{p}K_a\) が決定できないことを示しました。
しかし、問題はそれだけにとどまらないのです。
例えば2つの強酸を用意したとします ( 塩化水素 \(\text{HCl}\) と硝酸 \(\text{HNO}_3\) など )。
これらを個別に用意した水に溶解させ、濃度が等しくなるように調製します。
そしてそれぞれの水溶液の水素イオン濃度を測定すると何が分かるでしょうか。
答えは、塩酸も硝酸も水中では完全に電離するため、水素イオン濃度は両方等しくなるということです。
ところが上記の状況では塩酸と硫酸それぞれの間で水素イオンの供与能力に違いが無く、強度の比較ができないということに気がつくことでしょう。
これこそが重要な問題点なのです。
なぜこのようなことが起きるかと言うと前項の繰り返しになってしまいますが、
溶媒に水を利用している限り、その系に存在し得る最も強い酸および最も強い塩基とはそれぞれオキソニウムイオンと水酸化物イオンだからです。
このように、種類の異なる強酸 ( あるいは強塩基 ) の強度を知ろうとしても、両方ともオキソニウムイオンの酸性度 ( 塩基の場合は水酸化物イオンの塩基性度 ) と同等のレベルに均されてしまう効果を
水平化効果と呼びます。
これは前項の内容の言い換えでもあり、オストワルドの希釈律が成立しないために解離定数を求められないと言うよりも、水平化効果によって強酸・強塩基の本来の能力が隠される点が本質的な問題なのです。
結局のところ強酸・強塩基のpkaを求めるには
では、強酸の \(\text{p}K_a\) は求めることができないのかと言うとそうではありません。
実際に調査してみると分かることではありますが、\(\text{p}K_a\) の報告例はたくさん見つけることができます。
例えば塩化水素の場合、\(\text{p}K_a \simeq -7\) として一般的な書籍にも掲載されています。
更にもっと荒っぽい計算では、オストワルドの希釈律を近似的に利用して無理やり \(\text{p}K_a\) を求めるような練習問題なんかもあったりするようです。
つまり強酸であるという理由で \(\text{p}K_a\) を求めることができないなどということは無いということです。
ただオストワルドの希釈律を利用しての算出方法は前述の通り現実的ではありません。
そのため、強酸や強塩基の \(\text{p}K_a\) は水に溶解させて水素イオン濃度を測定するのとは別の分析手法で測定されます。
例えば次のような分析手法です。
・蒸気圧を利用した測定
・UV-Visの利用
・NMRの利用
しかし残念ながら当ページで詳細に触れる余裕は無いため割愛させていただきます。
※時が訪れたら、コンテンツを作ることにします。
比較
とは言え、
文中の各所で「水中」における話であることを示してきましたが、つまり水を利用したために生じる問題なのです。
なぜ \(\text{p}K_a\) を求めることができないのか再度言っておくと、
溶質である酸あるいは塩基の一部の分子だけが電離することによって達成される平衡状態とは、溶質の \(\text{p}K_a\) が0から14の間である必要があるからです。
強酸および強塩基ではこの範囲を優に超えてしまうため、それらはほぼ完全に電離してしまうのが原因でした。
この問題を解決する方法は、
それならば、測定したいpkaをカバーできる溶媒を選択すればいいということになる
例えば、酢酸を溶媒として見るとどうだろうか
酢酸の自己プロトリシス定数は \(3.5 \times 10^{-15}\) である。
また酢酸のpkaは4.76であることを考慮すると、水と比較してマイナス領域をカバーしていることが分かる
つまり酢酸を利用すると強酸の比較ができる
実際に、こういった様々な溶媒を上手く選択することによって塩酸は -7 硝酸は-1.4 硫酸 -2 と言った具合に強酸の酸解離定数を求めることができる
硫酸のほうが塩酸より酸性度が強いのでは?と思っていた方もいるかも知れない名前負けしている
-----雑記---------------------------------------------------------------------------
・ブレンステッドの定義によって、酸および塩基は相対的に決定されることを示しました。
どうしてこの反応が起こるのか、考える
・HAが水に水素イオンを供給しやすいから
・オキソニウムイオンが陰イオンに水素イオンを供給しやすいから
そしてこの平衡点は酸および共役酸の酸解離定数によって、右に傾いたり左に傾いたりする
つまり、物質次第ではほぼ電離度が1となるような酸も存在することになる
\[
\text{HA} + \text{H}_2\text{O} ~ \rightarrow ~ \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+
\]
言い換えれば、オキソニウムイオンよりも更に強い水素イオン供給能をもつ酸である
これにはまずオキソニウムイオンの酸解離定数を定めるところから始める必要があるだろう
\[
\text{H}_3\text{O}^+ + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+
\]
\[
K_{a (\text{H}_3\text{O}^+)} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 1 \\[15pt]
\therefore ~ \text{p}K_{a (\text{H}_3\text{O}^+)} = 0
\]
なるほど、酸解離定数pkaは小さいほど強いのであったから 0 よりも小さければいいということになる。Kaの場合は大きいほど酸性がつよい
つまり少なくとも以下の条件をクリアしている必要があるということだ
\[
\text{p}K_a < 0 ~ \Leftrightarrow ~ K_a > 1
\]
逆に塩基の場合も
\[
\text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} ~ \rightleftharpoons ~ \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-
\]
\[
K_{b (\text{OH}^-)} = \frac{[\text{OH}^-]}{[\text{OH}^-]} = 1 \\[15pt]
\therefore ~ \text{p}K_{b (\text{OH}^-)} = 0
\]
\[
\text{p}K_b < 0 ~ \Leftrightarrow ~ K_b > 1
\]
これが強酸や強塩基の数学的な素性のようだ
しかしながら、事実上完全に解離してしまう反応に置いて酸解離定数を上手く定めることができない
強酸は水に溶解させると、事実上完全に解離してしまうため、酸解離定数を定めることが出きない
なぜなら、分母が0になって発散してしまうため
またこれに紐付いて生じる問題もある
●水平化効果
強酸を水に溶解させると、事実上完全に解離する
実際、0.1Mの強酸を水に溶解させ、水素イオン濃度を測定すると0.1Mとなる
ところで pkaが0以下の酸は1つではない
何度も述べるが比較によって決まるために、理論上上限はない(絶対的な酸は存在しない)
ここにある2つの酸を用意したとする
例えば塩酸と硝酸としよう 0.1M用意した
これらの酸解離定数を求めたいため、水に溶解させて水素イオン濃度を測定する
しかし、それぞれの水溶液の水素イオン濃度は0.1Mとなった
入れた酸の量と同じだけの水素イオンの濃度となるために、完全に解離する強酸である
しかし、これではこれら2つの酸で強度を比較することができない
水中に置いて最も強い酸というのは既に定められていることにある
逆に最も強い塩基も決まっている
それはオキソニウムイオンと、水酸化物イオンである
強い酸の共役塩基は非常に水素イオン受容能が低いため、酸の状態で系内に存在することができません。
逆に強い塩基も共役酸は非常に水素イオン供与能が低いために、塩基の状態で系内に存在することができない。
つまり、塩酸と硝酸について酸の強度を知ろうとしても、両方とも同じレベルに均されてしまう
同様に強塩基についても水酸化物イオンの塩基性度と同じレベルに均されてしまう
これを水平化効果という
しかしこれで諦めることはできません。
●自己プロトリシス定数
●phの定義
\[
- \log K_{\text{w}} = - \log [\text{H}_3\text{O}^+] - \log [\text{OH}^-] = 14 \\[15pt]
\text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+ ~ \rightleftharpoons ~
\]
●水平化効果
強酸
弱酸
---------------------------------------------------------------------------------