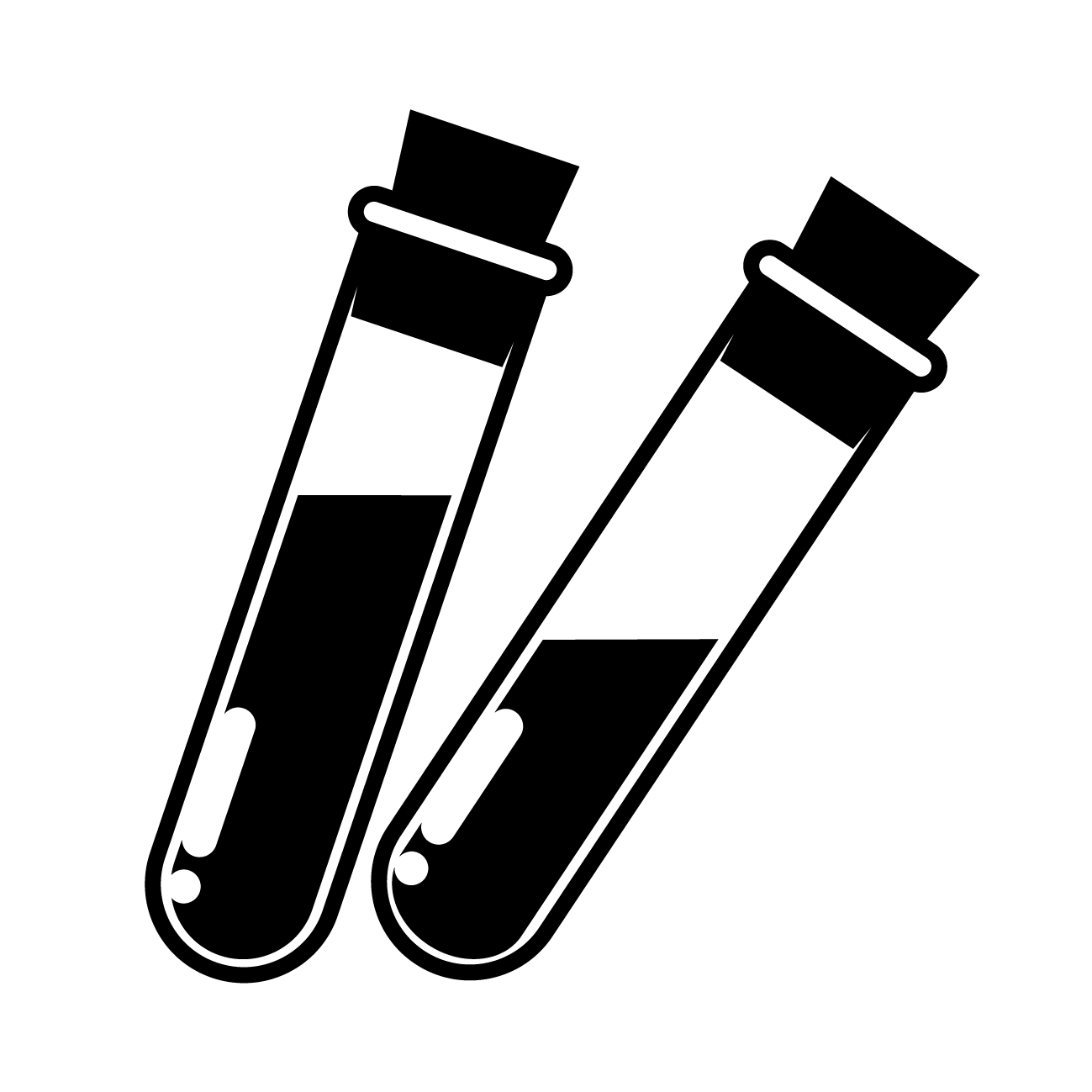私達がある事象に対して何らかの結論を得たいとき、原因となる要素をを足し合わせる操作を行うことが多いです。
しかし単に足し算を考えられる状況というのは実は特殊なケースだったりします。
そこで、ここではより応用が効く数学的解析手法である積分法を導入することにしましょう。
高度な解析手法ではありますが、その計算手続きは非常に簡単であることが示されます。
積分法の定義
積分法を実際に導入する前に、少し断って置かなければならないことがあります。
ここで紹介する積分法について、その研究自体は微分法の研究があったからこそ成し得たと言えます。
しかしながら、微分法と積分法の研究はそれぞれ独立して行われていた過去があり、すなわち積分法開発のために微分法が研究されたということではありませんでした。
ただし、研究が進むに連れてこれらは互いに逆演算であるということが明らかにされたことは確かです。
それについては後ほど触れることにしましょう。
話を積分法に戻しますが、この解析手法が編み出された目的とは複雑な形をした図形の面積を求めることにありました。
長方形は「縦 \(\times\) 横」という公式を利用して面積を求めることが可能ですが、もし仮にその内の1辺を曲線で置き換えた図形の面積を求めたい状況となったときどのように計算すればいいのでしょうか。
以下で詳細を見ていくことにします。
区分求積法
早速以下に示す図を見ていだきましょう。
図中の青色で示された領域は関数 \(f(x)\), \(x = a\), \(x = b\), \(x\) 軸で囲まれてできています。
この面積を求めたいとき、一部曲がった箇所が存在するため簡単に計算することができません。
そこで少し無理やりではありますが、すでに面積の求め方が既知である図形で領域内を埋め尽くせば正確では無いにしても凡そ近い値を得ることが可能でしょう。
当コンテンツでは長方形を敷き詰めて考えることにします。
ただし取り組み始める前に、取り決めを行っておく必要があります。
以下で数学的に取り扱っていくことになるので、無闇に敷き詰めても処理が煩雑になってしまうだけです。
具体的な取り決めとしては次に図でも示しましたが、用意した任意の幅の長方形について左上の頂点がグラフ上に乗るように配置する事としましょう。

これに従って、実際に長方形を敷き詰めた結果を以下に示します。

どうやらこれでは長方形の右上がグラフより上側にはみ出てしまっていて、得たい結果とは程遠くなってしまいそうです。
しかし、この考えのすごいところはここからです。
更に、各長方形の幅を狭くして敷き詰めていってみると、問題点は少しずつ軽減されていくのです。


長方形を100個も用意すると、冒頭で示したグラフで囲まれた図形とほぼ等しい状態になっています。このように、細かく分割することによって隙間を上手く埋めることができる事を視覚的に理解できたかと思われます。
ただ実際には長方形を敷き詰めたに過ぎないため、微量の誤差が生じてしまうのは否めません。
そこで極限の概念を利用して長方形の横幅を限りなく0に近づける操作を行ってみましょう。これは言わば求めたいグラフの面積と完全に等しい状態を作り出す後処理のようなものです。
極限操作とは、それを施すことによってただ1つの値に収束する必要があるのですが、
敷き詰める長方形の横幅を小さく取るにつれて目標にしている面積に近づいていることからも、この極限は収束してくれる事が期待できるわけです。
そしてこの極限値が得られるとき、その関数は \(a \leq x \leq b\) の範囲で積分可能であると表現されます。
それでは続いて、以上の内容を数学的に記述する方法を見ていきます。
積分を実行したい範囲 \(a \leq x \leq b\) に \(n\) 個の長方形を敷き詰めるものとします。

前述した取り決めに従って、それぞれの長方形は左上の頂点がグラフ上に乗るように配置しています。
このとき長方形の左辺の \(x\) 座標をそれぞれ \(x_i ~ (~ 1 \leq i \leq n ~)\) と置きます。
すると左から \(i\) 番目の長方形の横幅は \(x_{i + 1} - x_i\) となりますが、これを新たに \(\Delta x_i\) と置くことにし、
更に長方形の縦の長さが \(f(x_i)\) であるから長方形の面積は次のように記述することができることが分かります。
式(1)\[ f(x_i) \Delta x_i ~~~ (~ \Delta x_i \equiv x_{i + 1} - x_i ~) \]
この長方形を \(n\) 個全て足し合わせたものを求めたいため、和の記号 \(\Sigma\) を利用すれば良いでしょう。
式(2)\[ \sum_{i = 1}^n f(x_i) \Delta x_i \]
そして最後に、それぞれの長方形の幅 \(\Delta x_i\) を限りなく0に近づける極限操作 \(\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0}\) を施せば目標達成となります。
式(3)\[ \begin{align*} & \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i = 1}^n f(x_i) \Delta x_i \\[20pt] = & \lim_{\textcolor{red}{n \rightarrow \infty}} \sum_{i = 1}^n f(x_i) \Delta x_i \end{align*} \]
ところで、式(3)2行目に示しましたが、長方形の幅を小さくしていくに伴って考えている領域を敷き詰めるために必要な長方形の個数は増加していきますので \(n \rightarrow \infty\) と記述されることも多いです。
積分法の数学的記述を行うことに成功しましたが、その極限値である計算結果には特別な記号が与えられており \(\int\)(インテグラル)という記号を用いて次のように表現されます。
式(4)\[ \int_a^b f(x) dx \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i = 1}^n f(x_i) \Delta x_i \]
極限操作を行ったことによって
- 和の記号「 \(\Sigma\) 」が積分記号「 \(\int\) 」に変化した
- インデックス番号「 \(i : 1 \rightarrow n\) 」が積分範囲「 \(x : a \rightarrow b\) 」に変化した
- 長方形の幅「 \(\Delta x_i\) 」が微小量「 \(dx\) 」に変化した
と思っていただければ問題ありません。
積分の計算方法
前節では、面積の極限値として積分を定義しました。
当節では具体的な関数を例にして、実際に積分値を計算することを行いましょう。
定義に従って計算する
例として \(f(x) = x\) の場合を考えます。
式(4)に代入すると次の用になります。
式(5)\[ \int_a^b x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i = 1}^n x_i \Delta x_i ~~~ (~ \Delta x_i = x_{i + 1} - x_i ~) \]
ここから式変形していくのですが、一般に \(\Delta x_i ~ (1 \leq i \leq n)\) は一定値になるように設定します。
つまり、前節で説明した短冊状の長方形について、それぞれの横幅はどれも均等に取るのがベターということです。
※前節で示した長方形の横幅の定義( \(\Delta x_i = x_{i + 1} - x_i\) )のままだと、等間隔ではなくバラバラしている状況でも考えることが可能です。
これを数学的に表現すると、\(x = a\) から \(x = b\) の間を \(n\) 等分することになるので、
式(6)\[ \Delta x_i = \Delta x = \frac{b - a}{n} \]
となります。
長方形の幅を等間隔に設定した事によって、左から \(i\) 番目の長方形の位置 \(x_i\) は初項 \(a\), 公差 \(\Delta x\) の等差数列として表現しても良いことになります。
式(7)\[ x_i = a + i \Delta x \]
式(6), (7)を式(5)の右辺に代入して計算を進めてみましょう。
式(8)\[ \begin{align*} \sum_{i = 1}^n (a + i \Delta x) \Delta x &= \sum_{i = 1}^n a \Delta x + \sum_{i = 1}^n i (\Delta x)^2 \\[15pt] &= n a \Delta x + \frac{1}{2} n (n + 1) (\Delta x)^2 \end{align*} \]
式(8)の2行目に式変形するのに、和の公式 \(\sum_{k = 1}^n k = \frac{1}{2}n(n + 1)\) を利用しています。
\(\Delta x\) を式(6)を用いて式(8)を書き換えると更に計算ができて、
式(9)\[ \begin{align*} n a \Delta x + \frac{1}{2} n (n + 1) (\Delta x)^2 &= n a ~ \frac{b - a}{n} + \frac{1}{2} ~ (n^2 + n) \frac{(b - a)^2}{n^2} \\[15pt] &= a(b - a) + \frac{1}{2} (b - a)^2 + \frac{1}{2} \frac{(b - a)^2}{n} \\[15pt] &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} \frac{(b - a)^2}{n} \end{align*} \]
このようになります。
最後に極限 \(n \rightarrow \infty\) を実行すれば、式(9)の \(\frac{1}{2} \frac{(b - a)^2}{n}\) の項は0に収束してくれるため、結果として次の積分値が得られることが分かります。
\[ \int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \]
以上のように関数の積分値を求める具体的な手法を提供した訳ですが、実のところ少し大変な計算となっていることが分かるでしょうか。
今回例にあげた関数は冪関数という最も簡単な関数の1つであり、三角関数などの少し複雑な関数を扱う際には、もう少し骨の折れる計算を行う必要があるでしょう。
そこで、次の項ではより簡単に積分を実行できないか定理を導出することにします。
積分法の定理
前項で説明した積分の定義に従って積分値を求めるのには少しばかり大掛かりな作業になる事もあります。
この項では積分法の計算を楽にする定理を導きます。
そしてその過程で、積分と微分が互いに逆演算であることも示されます。
まず、ある関数 \(f(x)\) について、\(x\) 軸とで挟まれる領域の面積を考えましょう。
積分区間を \(a\) から \(x\) に取ったときの面積を \(S(x)\) と表記することにします。
式(10)\[ S(x) = \int_a^x f(x) dx \]
またこの積分範囲の右端を \(\Delta x\) だけ動かしときの面積は \(S(x + \Delta x)\) と表現することができます。
数学的には式(10)と同様に考えれば次のとおりに記述されることは良いでしょう。
式(11)\[ S(x + \Delta x) = \int_a^{x + \Delta x} f(x) dx \]
これらが表す面積を図示すると以下のようになります。

これから何を計算しようとしているかと言うと、「積分区間の増加に伴って面積はどのくらい増減するか」を表す量です。
したがって、\(x\) から \(x + \Delta x\) の間にある領域の面積に着目して解析を進めてみましょう。
これはちょうど式(11)から式(10)を引いた値に等しくなるはずです。
式(12)\[ S(x + \Delta x) - S(x) \]
解析を進めるために、式(12)が表す面積を拡大してみます。

図で見ていただければ、凡そ着目している領域の形状は台形に近い事がわかります。
そこで、図中に示した点線のように長方形と直角三角形に近似できるとして面積を計算してみると次式のようになることがお分かりでしょうか。
式(13)\[ S(x + \Delta x) - S(x) \simeq ~ f(x) \Delta x ~ + ~ \frac{1}{2} ~ \frac{df(x)}{dx} (\Delta x)^2 \]
式(13)右辺について、第1項が長方形、第2項が直角三角形の面積を表しています。確認してみてください。
ここから両辺を \(\Delta x\) で割って次式のようにすれば
式(14)\[ \frac{S(x + \Delta x) - S(x)}{\Delta x} \simeq f(x) + \frac{1}{2} \frac{df(x)}{dx} \Delta x \]
左辺は、前述した「積分区間の増加に伴って面積はどのくらい増減するか」を表す量になります。
すなわち \(x\) の変化 \(\Delta x\) に伴う面積の変化 \(\Delta S \equiv S(x + \Delta x) - S(x)\) です。
最後に \(\Delta x \rightarrow 0\) という極限を施せば、式(14)右辺の第2項が0となるためにより簡単な結果として得ることが期待できます。
更に左辺に至っては \(S\) の \(x\) 微分として姿を変えることも忘れてはいけません。すなわち次の通りになります。
式(15)\[ \frac{dS(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S(x + \Delta x) - S(x)}{\Delta x} = f(x) \]
※興味がある方は、不等式で評価して証明する厳密な方法を調べて見てください。
ここで、初め式(10)で定めたように \(S\) とは関数 \(f(x)\) の積分でした。式(10)を式(15)に代入してみましょう。
式(16)\[ \frac{d}{dx} \int_a^x f(x) dx = f(x) \]
得られる結果は、微分と積分に関する関係式となっています。
式(16)左辺は、「関数 \(f(x)\) を \(x\) で積分したものを、再度 \(x\) で微分すると元に戻る」ことを表しています。
つまり、微分と積分は互いに逆演算であると言うことができるのです。
これは微積分学において非常に重要な定理であり、微積分学の基本定理とも呼ばれます。
またこの定理(16)から、いま目的としている積分計算時に役立つ定理を導くことができます。目的までもう少し続きます。
これまで \(S(x)\) としてきた関数を改めて \(F(x)\) と表すことにします。これは慣習なので特に意味はありません。
式(17)\[ F(x) = \int_a^x f(x) dx \]
この \(F(x)\) には名称が与えられており、原始関数と言います。
一方で \(f(x)\) のことは被積分関数と呼ばれます。
原始関数とは、式(16)と合わせて考えれば非常に簡単なものであることが分かり、つまり微分すると \(f(x)\) になる関数ということです。
式(18)\[ \frac{d}{dx} F(x) = f(x) \]
例えば、\(f(x) = x\) を満たす原始関数は \(F(x) = \frac{x^2}{2}\) といった具合です。
ここであることに気がついた方は鋭いですが、次のように \(F(x)\) に定数 \(C\) を加えたものであっても式(18)と同様な関係が成立します。
式(19)\[ \begin{align*} & \frac{d}{dx}\left(F(x) + C\right) = f(x) \\[15pt] \Leftrightarrow ~ & \frac{d}{dx} F(x) + \frac{d}{dx} C = f(x) \\[15pt] \Leftrightarrow ~ & \frac{d}{dx} F(x) = f(x) ~~~ \left( ~ \because ~ \frac{dC}{dx} = 0 ~ \right) \end{align*} \]
なぜなら定数を微分しても0となるためです。
このことから、式(17)は次のように補正を加えた形式で書き表しても問題ないと言えるでしょう。
式(20)\[ F(x) + C = \int_a^x f(x) dx \]
ここまで理解できれば、後は目的の定理までは一気にたどり着くことができます。
\(x = a\) を代入してみましょう。
式(21)\[ F(a) + C = \int_a^a f(x) dx \]
このとき積分とは面積であることを思い出すと、積分区間が \(a\) から \(a\) というのは \(x\) 軸方向の幅は0のため、面積も0となります。
つまり式(21)の右辺は0なので、結果として補正定数 \(C\) を具体的に決定することができます。
式(22)\[ \begin{align*} F(a) + C &= \int_a^a f(x) dx = 0 \\[15pt] \therefore C &= -F(a) \end{align*} \]
そして式(22)と式(20)を合わせた結果が次のとおりです。
式(23)\[ F(x) - F(a) = \int_a^x f(x) dx \]
ここでもし \(x = b\) であったとすれば更に次のような表現にもなります。
式(24)\[ F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \]
この式(24)が目的としていた定理になります。
関数 \(f(x)\) を区間 \(a \leq x \leq b\) で積分した結果、原始関数に \(a\) および \(b\) を代入した値の差になるというのです。
最後に、\(f(x) = x\) の \(a \leq x \leq b\) における積分値を求めてみることにしましょう。
先程も少し触れましたが \(f(x) = x\) の原始関数は次のとおりです。
\[ F(x) = \frac{x^2}{2} + C \]
これより積分計算の結果は
\[ \begin{align*} \int_a^b x dx &= \left( \frac{b^2}{2} + C \right) - \left( \frac{a^2}{2} + C \right) \\[15pt] &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \end{align*} \]
となって前項と同じ値を得ることができました。
この様に積分法の定理を利用すれば、定義に従って和の計算を行うよりも圧倒的に計算が簡単になります。
ただし積分計算自体が難しい被積分関数もあるため、一概に簡単になったとは言えません。
それにも関わらず、積分計算が優れている理由は積分区間の末端のみを考えるだけで計算値を得ることができる点です。
この利点は今後絶大な威力を発揮してくれることになるため、必ず扱えるようになって置く必要があります。
【サイト運営 : だいご】
今年で物理化学歴12年目になります。
大学入試2次数学でたった3割しか得点できなかったいわゆる数弱落ちこぼれ。それでも好きこそものの上手なれと言ったところか、学会で最優秀賞受賞したり首席卒業できてしまったので、役に立つ知識を当サイトに全て惜しみなく公開しようと思います。ブックマークをオススメ。