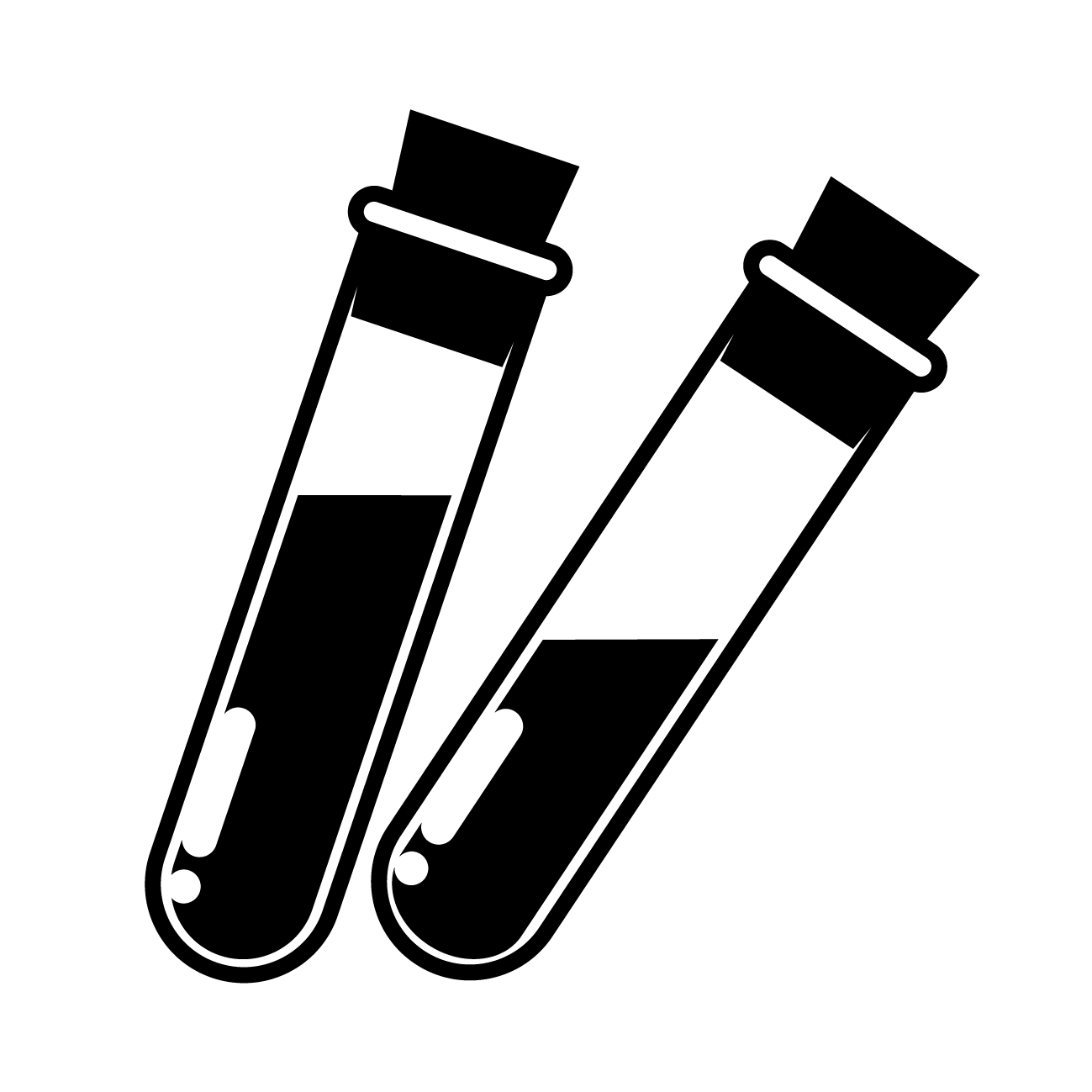溶液は一般に理想的に振る舞わず、理想溶液と区別するために実在溶液と呼ばれます。
ここでは実在溶液が示す挙動と、実在溶液を取り扱うための概念である活量について詳しく解説していきます。
■このページで分かる内容のまとめ■
実在溶液は理想溶液とは異なり理想的ではない挙動を示します。
溶液中の成分 \(i\) の化学ポテンシャルを記述する際、理想からのズレを加味した補正を行わなければなりません。
そこで活量 \(a_i\) と呼ばれる実効的な濃度を用いた次式が用いられます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln a_1 \]
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln a_i \]
実在溶液
実在溶液は理想溶液とは異なり理想的な振る舞いを示さない溶液を指します。
溶液が理想的な振る舞いをするとき、以下のような性質を満たします。
- \(\Delta V_\text{mix} = 0\) ( 混合体積変化 )
- \(\Delta H_\text{mix} = 0\) ( 混合エンタルピー変化 )
- \(\Delta G_\text{mix} = RT \sum_{i = 1}^r x_i \ln x_i\) ( 混合ギブス自由エネルギー変化 )
- \(\Delta S_\text{mix} = -R \sum_{i = 1}^r x_i \ln x_i\) ( 混合エントロピー変化 )
- \(P_i = P^*_i x_i\) ( ラウールの法則 )
一方で、実在溶液の調製では理想混合の性質は満たしませんし、任意の混合比でラウールの法則が成立するとも言えません。
実在溶液の非理想性
実在溶液は、理想溶液のように理想的な振る舞いはしません。
例えば、水 50 \([\text{mL}]\) とエタノール 50 \([\text{mL}]\) の混合を考えましょう。
これらが理想的に振る舞うとすると、混合溶液の総体積は 100 \([\text{mL}]\) になるはずです。しかし実際には凡そ 95 \([\text{mL}]\) となって、期待より小さい体積になります。
このように実在溶液では、理想溶液の性質を一般に満たさない挙動を示します。
その他、実在溶液は一般に蒸気圧がラウールの法則に従わず複雑な挙動を示します。
次の図を見てください。


これは2種の液体を任意の比率で混合させた場合の蒸気圧のグラフです。下側の交差している実線が単成分が示す蒸気圧、上側の実線が全蒸気圧を表しています。
破線は溶液が理想的に振る舞った場合の蒸気圧挙動、すなわちラウールの法則を表したグラフです。
実線で示した実在溶液の蒸気圧挙動は理想から大きく外れていることが分かるでしょう。
また混合する物質によって蒸気圧が理想より大きくなる場合や小さくなる場合があるため、実際の挙動は実験的に測定する必要があります。
実在溶液の化学ポテンシャルと活量
気液平衡状態にある溶液中の成分 \(i\) の化学ポテンシャルは、その蒸気圧 \(P_i\) を用いて次式で記述することができます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{P_i}{P^*_i} \]
- \(\mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}})\) : 溶液中の成分 \(i\) の化学ポテンシャル
- \(\mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P)\) : 純粋な液体成分 \(i\) の化学ポテンシャル
- \(P_i\) : 成分 \(i\) の蒸気圧
- \(P^*_i\) : 純粋な成分 \(i\) の蒸気圧
ここで気相は各成分 \(i\) の蒸気からなる混合気体であり、蒸気圧 \(P_i\) は分圧を表します。他方 \(P^*_i\) は純粋な成分 \(i\) が気液平衡にあるときの蒸気圧です。
溶液の化学ポテンシャルが式(1)で表されることは下記関連コンテンツで詳しく説明をしているので参考にしてください。
式(1)を用いれば理想溶液か実在溶液に依らず、溶液中の成分 \(i\) の化学ポテンシャルを求めることができます。
蒸気圧 \(P_i\) を含んでおり、溶液に着目したいにも関わらず気相の情報も要求されるとのことですが、これはラウールの法則 \(P_i = P^*_i x_i\) およびヘンリーの法則 \(P_i = H_i x_i\) によって回避できます。
ただし2つの法則は適用されるべき箇所が異なり、それぞれ…
- ラウールの法則 : 過剰量の溶媒について成立する法則
- ヘンリーの法則 : 過少量の溶質について成立する法則
という違いがあります。
以下で詳細に触れてきましょう。
溶媒の化学ポテンシャル
以下 \(i = 1\) の成分を溶媒として扱うことにします。
溶媒の化学ポテンシャルは前述の通りラウールの法則を用いることで得られ、実際に式(1)に対して \(P_1 = P^*_1 x_1\) を代入すると直ちに次の式が導かれます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln x_1 \]
式(2)は理想溶液中の成分の化学ポテンシャルと等しくなります。詳細はラウールの法則の導出を解説したページを参照してください。
さて、本題はラウールの法則がなぜ溶媒に対して適用されるのかという事。
それを理解するために、実在溶液の蒸気圧挙動を表したグラフを見てみましょう。

簡単のために2成分系で考えます。
着目するのは単成分の蒸気圧曲線 上端付近。\(x_\text{A} \simeq 1\) 付近は成分Aが過剰、逆に \(x_\text{B} \simeq 1\) 付近は成分Bが過剰な状況を表します。
\(x_\text{A} \simeq 1\) または \(x_\text{B} \simeq 1\) 付近では、実際の蒸気圧の挙動を表した実線と、理想的な蒸気圧の挙動を表した破線との差が小さいため、溶媒に対して近似的にラウールの法則が適用できるということです。
しかし溶液全体に対して溶質の量が増加すると、理想からのズレは大きくなり式(2)は適用できなくなります。
実在溶液の挙動を記述するためには、この理想からのズレを補正しなくてはなりません。
次式に示すように活量係数と呼ばれる量 \(\gamma_1\) を用いて、理想からのズレに相当する補正項を加えます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln x_1 + \textcolor{red}{RT \ln \gamma_1} \\[15pt] \]
補正項に対数を用いたのは、次式の様に活量係数をモル分率との積として まとめられるためです。
\[ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln \gamma_1 x_1 \]
ここで新たに活量 \(a_1\) を導入します。
\[ a_1 \equiv \gamma_1 x_1 \]
すると式(4)は次のように書き換えられます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln a_1 \]
補正前の式(2)と比較してみましょう。
\[ \begin{align*} &\text{eq(2) :} ~~~~~ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln \textcolor{red}{x_1} ~~~ \big( ~ \text{ideal behavior : } x_1 \rightarrow 1 ~ \big)\\[15pt] &\text{eq(6) :} ~~~~~ \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_1(T, ~ P) + RT \ln \textcolor{red}{a_1} ~~~ \big( ~ \text{real behavior} ~ \big) \end{align*} \]
2つの式は共に同様の形式になっており、溶液が理想的に振る舞うときは対数項にモル分率、非理想的に振る舞うときは対数項に活量が使われるという違いのみです。
またこの比較により、活量が実在溶液における実効的な濃度であるとの解釈もできるでしょう。
溶質の化学ポテンシャル
前述した通り、溶質が過少量である溶液については、ヘンリーの法則を用いて化学ポテンシャルを記述できます。
この過少量の溶質が溶解した溶液のことを理想希薄溶液と呼び、その名称どおり理想的な振る舞いをするのが特徴です。
それを2成分系の蒸気圧のグラフを例に確認してみましょう。

今度は単成分の蒸気圧曲線 下端付近に着目します。\(x_\text{A} \simeq 0\) 付近は成分Aが希薄、逆に \(x_\text{B} \simeq 0\) 付近は成分Bが希薄な状況を表します。
また実際の蒸気圧の挙動を表した実線に対して \(x_\text{A} = 0\) および \(x_\text{B} = 0\) から引かれた接線、これらがヘンリーの法則 \(P_\text{A} = H_\text{A} x_\text{A}\) および \(P_\text{B} = H_\text{B} x_\text{B}\) を表した直線になっています。
当然、接点付近の \(x_\text{A} \simeq 0\) あるいは \(x_\text{B} \simeq 0\) では実線と接線の差は小さいため、理想希薄溶液では溶質に対してヘンリーの法則が近似的に成立すると言えます。
以下で、実際に溶質の化学ポテンシャルを求めてみましょう。
溶液中の成分の化学ポテンシャルを表した式(1)にヘンリーの法則 \(P_i = H_i x_i ~ ( ~ i ~ \char`≠ ~ 1 ~ )\) を代入します。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{H_i x_i}{P^*_i} \]
更に式(7)を変形して \(RT \ln x_i\) の項を分離します。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{H_i}{P^*_i} + RT \ln x_i \]
ここで次に示す化学ポテンシャルと同じ次元をもつ \(\mu^\circ_i(T, ~ P)\) を定めて
\[ \mu^\circ_i(T, ~ P) \equiv \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P) + RT \ln \frac{H_i}{P^*_i} \]
式(8)を式(9)で置き換えれば、溶質の化学ポテンシャルが得られます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln x_i \]
※ 式(10)で溶質のモル分率を \(x_i = 1\) とすると
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) \]
が成立しますが、\(\mu^\circ_i(T, ~ P)\) は純粋な成分 \(i\) の化学ポテンシャルではありません。純粋な成分 \(i\) の化学ポテンシャル \(\mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P)\) は式(9)から次式で与えられます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P) = \mu^\circ_i(T, ~ P) - RT \ln \frac{H_i}{P^*_i} \]
\(\mu^\circ_i(T, ~ P)\) は仮想的な量で、ヘンリーの法則 ( \(x_i = 0\) における蒸気圧曲線の接線 ) が任意の混合比で成り立つとした場合の \(x_i = 1\) における値を指します。

溶媒全体に対して溶質の量が増加すると、溶媒の化学ポテンシャルの非理想性が現れるのと同様に、溶質の化学ポテンシャルも非理想的に振る舞います。
溶質についても理想的な挙動からのズレを補正するために活量係数 \(\gamma_i\) を導入し、次式のように式(10)に補正項を加えます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln x_i + \textcolor{red}{RT \ln \gamma_i} \]
対数法則を用いて整理すると
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln \gamma_i x_i \]
溶質の活量係数とモル分率の積を新たに活量 \(a_i\) として定義します。
\[ a_i \equiv \gamma_i x_i \]
したがって、式(13)を式(12)に代入すると実在溶液における溶質の化学ポテンシャルが得られます。
\[ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln a_i \]
補正前の式(10)と比較してみましょう。
\[ \begin{align*} &\text{eq(10) : } ~~~~~ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln \textcolor{red}{x_i} ~~~ \big( ~ \text{ideal behavior : } x_i \rightarrow 0 ~ \big) \\[15pt] &\text{eq(14) : } ~~~~~ \mu^{\text{(L)}}_i(T, ~ P; ~ \boldsymbol{n}^{\text{(L)}}) = \mu^\circ_i(T, ~ P) + RT \ln \textcolor{red}{a_i} ~~~ \big( ~ \text{real behavior} ~ \big) \end{align*} \]
扱っている系が理想希薄溶液であるなら式(10)、そうでなければ式(14)を用いれば良いです。その際、活量は実験的に求める必要があります。
【サイト運営 : だいご】
今年で物理化学歴12年目になります。
大学入試2次数学でたった3割しか得点できなかったいわゆる数弱落ちこぼれ。それでも好きこそものの上手なれと言ったところか、学会で最優秀賞受賞したり首席卒業できてしまったので、役に立つ知識を当サイトに全て惜しみなく公開しようと思います。ブックマークをオススメ。