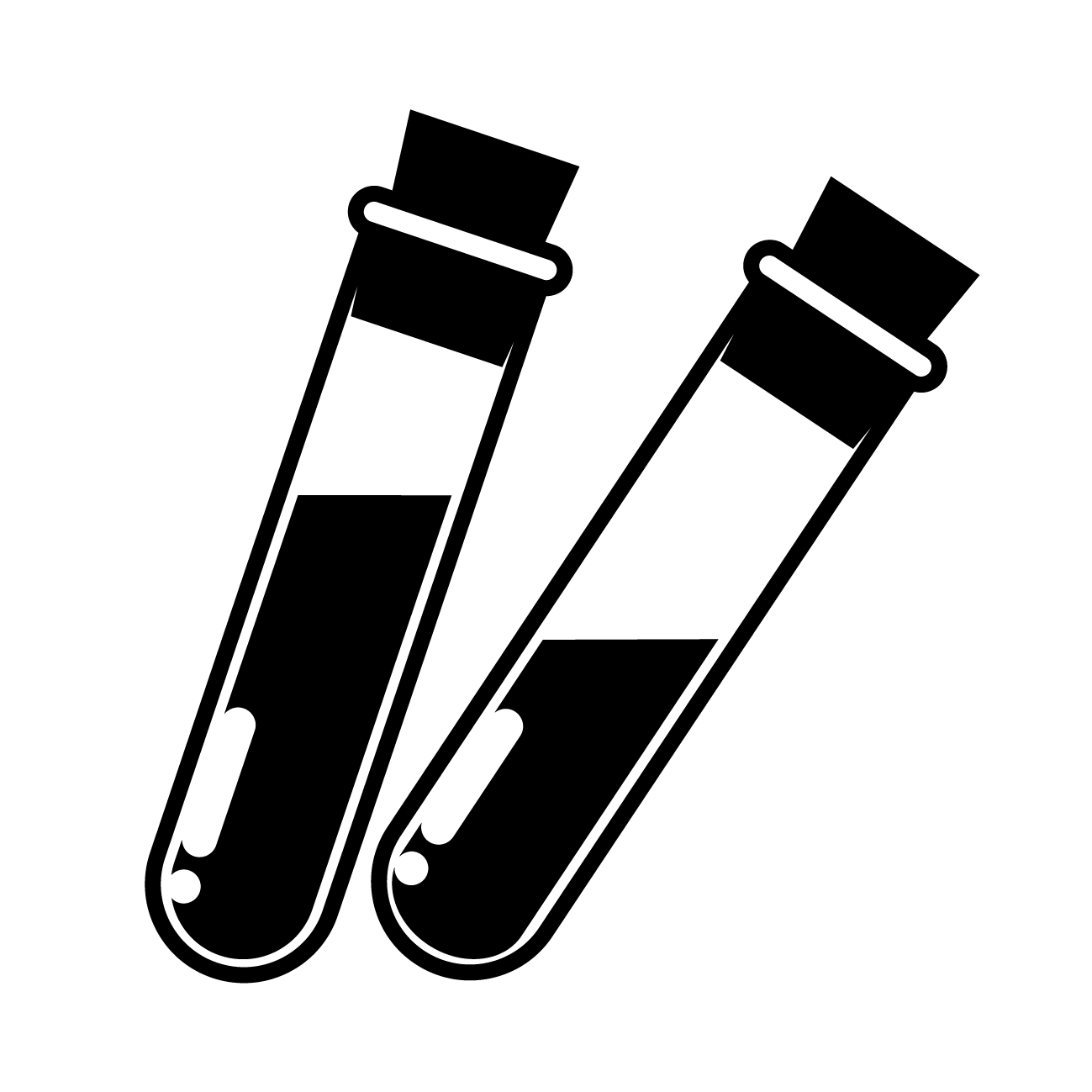ここでは等温環境下で系がする等温最大仕事と、それを利用して定義できるヘルムホルツ自由エネルギーについて詳しく解説していきます。
■このページで分かる内容のまとめ■
等温環境下に置かれた系が外界にする仕事を等温仕事と言い、特に準静的過程においては等温最大仕事をします。
等温最大仕事 \(W_\text{max}\) は次式のように系の圧力を体積で積分することによって求めることができます。
\[ W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n) \big) = \int_{V_\text{A}}^{V_\text{B}} PdV \]
等温最大仕事は上式のように積分によって与えられるため、積分区間の上端と下端すなわち操作前後の平衡状態が定まれば一意に決まる量であることが分かります。
また等温最大仕事を用いて、ヘルムホルツ自由エネルギーを導入することができ、それぞれは次の関係によって結ばれます。
\[ F(T; ~ V_\text{A}, ~ n) - F(T; ~ V_\text{B}, ~ n) = W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n) \big) \]
ヘルムホルツ自由エネルギーは状態量であり、変化前後の系の平衡状態によって一意に定まります。
ヘルムホルツ自由エネルギー \(F\) そのものは内部エネルギー \(U\) とエントロピー \(S\) を用いて次のように与えられます。
\[ F = U - TS \]
またヘルムホルツ自由エネルギーの体積および温度依存性から、系の圧力やエントロピーを求めることができます。
\[ \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T, ~ n} = -P \]
\[ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V, ~ n} = -S \]
■目次■
等温仕事
等温仕事とは
等温環境下に置かれた系が外界にする仕事を等温仕事と言います。
例えば系に対して次の等温操作をした場合を考えましょう。
\[ (T; ~ V_\text{A}, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{i}} ~ (T; ~ V_\text{B}, ~ n) \]
操作(1)は等温操作なので操作前後で温度の変化はありません。
このとき等温仕事を \(W\) とすると、最大仕事の原理に従って次のように記述することができます。
\[ W \leq W_\text{max} \]
式(1)中の \(W_\text{max}\) は最大仕事であり、等温条件においては等温最大仕事と呼ばれます。
等温最大仕事
等温操作において最も重要であるのは等温最大仕事です。
等温最大仕事は等温環境下に置かれた系を準静的に操作したときに系がし得る最大の仕事を言います。
一般に最大仕事は系の圧力と体積変化の積 \(P dV\) の積分によって表現でき、圧力の関係式 \(P = P(T; ~ V, ~ n)\) が明らかな場合は次式に代入して計算することで最大仕事を求めることが可能です。
\[ W_\text{max} = \int_{V_\text{A}}^{V_\text{B}} P dV \]
例えば理想気体を取り扱う場合、圧力表式は理想気体の状態方程式に従って \(P = \frac{nRT}{V}\) を用いれば最大仕事を求めることができます。
この等温準静的操作について、以降では次のように表現することにします。
\[ (T; ~ V_\text{A}, ~ n) ~ \xleftrightarrow{\text{iq}} ~ (T; ~ V_\text{B}, ~ n) \]
矢印上部の「 iq 」は "等温準静的" を英語で表した "quasi-static isothermal" の頭文字を表しています。また操作(2)は逆操作も可能なので、矢印は両方へ向いています。
更に最大仕事の重要性はそれだけではなく、最大の魅力は積分区間の上端と下端を定めれば仕事量は一意に決まることです。
つまり操作(1)における等温最大仕事は、操作前後の系の体積 \(V_\text{A}\) および \(V_\text{B}\) によって値が決まるのです。
そのため等温最大仕事は次のように操作前後の状態を用いて記述することにします。
\[ W_\text{max} \big(T; (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n)\big) \]
等温最大仕事の性質
等温最大仕事について次の性質を説明しておきます。
- 相加性
- 示量性
- 逆操作における等温最大仕事
相加性
次の一連の操作を考えたとき、系が操作全体でする仕事は、それぞれの操作における等温最大仕事の和に等しくなります。
\[ (T; ~ V_\text{A}, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{iq}} ~ (T; ~ V_\text{B}, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{iq}} ~ (T; ~ V_\text{C}, ~ n) \]
つまり操作(3)を全体で見ると、系は状態A \((T; ~ V_\text{A}, ~ n)\) から状態C \((T; ~ V_\text{C}, ~ n)\) に変化しているので、等温最大仕事は \(W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{C}, ~ n) \big)\) と書けます。
そして系がする正味の等温最大仕事は状態AB間と状態BC間での等温最大仕事の和で表現されるので、以上のことから等温最大仕事は次に示す和の関係が成立することが分かるでしょう。
\[ \begin{align*} &W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{C}, ~ n) \big) \\[15pt] &= W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n) \big) + W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{B}, ~ n) \rightarrow (V_\text{C}, ~ n) \big) \end{align*} \]
示量性
等温最大仕事には示量性があるとし、系を \(\lambda\) 倍すれば等温最大仕事も \(\lambda\) 倍になるものとします。
\[ W_\text{max}\big(T; ~ (\lambda V_\text{A}, ~ \lambda n_\text{A}) \rightarrow (\lambda V_\text{B}, ~ \lambda n_\text{B}) \big) = \lambda W_\text{max}\big( T; ~ (V_\text{A}, ~ n_\text{A}) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n_\text{B}) \big) \]
逆操作における等温最大仕事
操作(2)で示したように、等温準静的操作は逆向きの変化が可能です。
このとき系がする等温最大仕事は \(W_\text{max}\big(T; ~ (V_\text{B}, ~ n) \rightarrow (V_\text{A}, ~ n) \big)\) と書けます。
これは式(3)で与えた等温最大仕事の積分区間をちょうど逆にしたものに等しいので、直ちに次の関係が成立すること分かります。
\[ W_\text{max} \big(T; (\textcolor{red}{V_\text{B}}, ~ n) \rightarrow (\textcolor{red}{V_\text{A}}, ~ n)\big) = -W_\text{max} \big(T; (\textcolor{red}{V_\text{A}}, ~ n) \rightarrow (\textcolor{red}{V_\text{B}}, ~ n)\big) \]
また式(6)を次式のように書き換えると…
\[ W_\text{max} \big(T; (V_\text{B}, ~ n) \rightarrow (V_\text{A}, ~ n)\big) + W_\text{max} \big(T; (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n)\big) = 0 \]
となって、系を初期状態から準静的に操作して元の状態に戻すとき、系の外部も一緒に元の状態に戻ると解釈できる関係が導かれます。
ケルビンの原理
準静的ではない操作では、最大仕事の原理 ( 式(1) ) に従って系は最大仕事より小さな仕事をすることになります。
そしてこの事から系が準静的ではない過程を経由して初期状態に戻るとき、系は外界に対して負の仕事をするというケルビンの原理が導かれます。
すなわち式(7)のようにトータルの仕事量が 0 とはならず、系が初期状態に戻ったとしても外部には影響が残ってしまうということです。
例えば次の操作を考えたとき
\[ (T; ~ V_\text{A}, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{i}} ~ (T; ~ V_\text{B}, ~ n) ~ \xrightarrow{\text{i}} ~ (T; ~ V_\text{A}, ~ n) \]
各操作における等温仕事を \(W^{\text{A} \rightarrow \text{B}}\)、\(W^{\text{B} \rightarrow \text{A}}\) とすると最大仕事の原理から
\[ \begin{align*} W^{\text{A} \rightarrow \text{B}} < W_{\text{max}}(T; ~ (V_{\text{A}}, ~ n) \rightarrow (V_{\text{B}}, ~ n)) \\[15pt] W^{\text{B} \rightarrow \text{A}} < W_{\text{max}}(T; ~ (V_{\text{B}}, ~ n) \rightarrow (V_{\text{A}}, ~ n)) \end{align*} \]
が成立します。
式(8)の両辺で足し合わせれば、次式が得られます。
\[ W^{\text{A} \rightarrow \text{B}} + W^{\text{B} \rightarrow \text{A}} < 0 \]
式(9)右辺は、式(7)を利用して 0 に置き換えました。
一方で左辺は系の体積を \(V_\text{A}\) から \(V_\text{B}\) にして、再度 \(V_\text{A}\) に戻したときの正味の仕事を表しています。
このように系を操作して元の状態に戻す際に準静的ではない過程を経由させたとき、系は外界に対して負の仕事をすることが分かります。
ヘルムホルツ自由エネルギー
断熱仕事分だけ変化する内部エネルギーを定義できたように、等温最大仕事分だけ変化するエネルギーを定義できます。
そのエネルギーをヘルムホルツ自由エネルギーと言って \(F(T; ~ V, ~ n)\) で表します。
要するに、等温最大仕事とヘルムホルツ自由エネルギーは次に示す関係にあるということです。
\[ F(T; ~ V_\text{A}, ~ n) - F(T; ~ V_\text{B}, ~ n) = W_\text{max}\big(T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n) \big) \\[15pt] \Delta F = - W_\text{max}\big(T; ~ (V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (V_\text{B}, ~ n) \big) \]
とは言え、熱力学系の総エネルギーである内部エネルギー \(U\) があるにも関わらずわざわざ別のエネルギーを導入する意義はあるのでしょうか?
等温最大仕事とヘルムホルツ自由エネルギーの関係式(10)を手っ取り早く理解するなら、等温条件において成立するエネルギー保存の法則と言うことができます。
同様に断熱仕事と内部エネルギーについて言えば断熱条件において成立するエネルギー保存の法則となります。
つまり系が置かれている状況に合わせてエネルギーを使い分けると便利であるということです。
それに、もし内部エネルギー変化が等温最大仕事に等しいとすると実際不都合が生じてしまうのです。
\[ U(T; ~ V_\text{A}, ~ n) = U(T; ~ V_\text{B}, ~ n) + W_{\text{max}}\big(T; ~ (V_{\text{A}}, ~ n) \rightarrow (V_{\text{B}}, ~ n)\big) ~~~ (?) \]
例えば \(V_\text{B} = V_{\text{A}} + \Delta V\) と置いてテイラー展開の適用を適用すると \(U(T; ~ V_\text{B}, ~ n)\) について
\[ \begin{align*} U(T; ~ V_\text{B}, ~ n) &= U(T; ~ V_{\text{A}} + \Delta V, ~ n) \\[15pt] &\simeq U(T; ~ V_\text{A}, ~ n) + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, ~ n} \Delta V \end{align*} \]
と式変形できるので、結局式(11)は次のように書き換えることができます。
\[ 0 \simeq \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, ~ n} \Delta V + W_{\text{max}}\big(T; ~ (V_{\text{A}}, ~ n) \rightarrow (V_{\text{B}}, ~ n)\big) \]
ここで内部エネルギーの体積に関する偏微分係数 \(\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)\) がほとんど 0 に近い事を思い出しましょう。
すると系の体積変化 \(\Delta V\) の大きさに関わらず、常に等温最大仕事は 0 に近くなってしまう事が分かります。
これは明らかに矛盾した結果を導くことになるのです。
このような理由から、内部エネルギーとは異なるエネルギー ( すなわちヘルムホルツ自由エネルギー ) を導入する意義はあると言えるでしょう。
ヘルムホルツ自由エネルギーの性質
ヘルムホルツ自由エネルギーが等温最大仕事を用いて導入したことからも分かるように、ヘルムホルツ自由エネルギーは等温最大仕事の性質を受け継ぎます。
繰り返しになりますが、等温最大仕事は
- 相加性
- 示量性
があるので、ヘルムホルツ自由エネルギーについても同じく成り立つ性質となります。
またヘルムホルツ自由エネルギーは「状態量」であることも非常に重要です。
相加性
異なる単一系を複合させたとき、複合系全体のエネルギーは複合前の単一系におけるエネルギーの総和に等しくなります。
例えば、系1と系2についてヘルムホルツ自由エネルギーがそれぞれ \(F_1(T; ~ V_1, ~ n_1)\)、\(F_2(T; ~ V_2, ~ n_2)\) であるとき、それぞれを複合した系の総エネルギーは
\[ F_1(T; ~ V_1, ~ n_1) + F_2(T; ~ V_2, ~ n_2) \]
となります。
示量性
系を \(\lambda\) 倍にしたときのエネルギーは、スケールする前のエネルギーの \(\lambda\) 倍になります。
すなわち次式の成立が言えます。
\[ F(T; ~ \lambda V, ~ \lambda n) = \lambda F(T; ~ V, ~ n) \]
状態量としての性質
ヘルムホルツ自由エネルギーは状態量であり、系の状態 \((T; ~ V, ~ n)\) が決まれば値も一意に定まります。
繰り返しになりますが、ヘルムホルツ自由エネルギーは等温最大仕事を用いて定義されるもので、最大仕事量は式(2)で与えられるように積分区間に依存しています。
式(10)に式(2)を代入してみると
\[ F(T; ~ V_\text{A}, ~ n) - F(T; ~ V_\text{B}, ~ n) = \int_{V_\text{A}}^{V_\text{B}} PdV \]
となり、すなわち系が変化する前後のヘルムホルツ自由エネルギーは式(15)の右辺の積分区間によって決まると言うことができます。
そしてエネルギーを 0 とする適当な基準点O \((T; ~ V_\text{O}, ~ n)\)を定めることで、次式のように積分区間の上端が決まればヘルムホルツ自由エネルギーが一意に定まることが分かります。
\[ F(T; ~ V_\text{B}, ~ n) = -\int_{V_\text{O}}^{V_\text{B}} PdV \]
ヘルムホルツ自由エネルギーによる圧力の表現
ヘルムホルツ自由エネルギーを用いて系の圧力を計算することができます。
式(16)から、圧力 \(P\) を体積 \(V\) について積分した結果がヘルムホルツ自由エネルギー \(F\) となることから、逆にヘルムホルツ自由エネルギーを体積について偏微分すれば圧力が求められることが直ちに分かります。
\[ \left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, ~ n} = -P \]
つまり系のヘルムホルツ自由エネルギーが分かれば自動的に系の圧力も求められた事になるのです。
これは熱力学の面白い所でもあり、式(17)以外にもどの熱力学量から別の熱力学量が導けるかを理解しておくことが重要です。
ヘルムホルツ自由エネルギーと内部エネルギーの関係
等温条件下で扱い易いエネルギーとしてヘルムホルツ自由エネルギーを導入しましたが、内部エネルギー ( 熱力学系の総エネルギー ) と比較してそれが意味する実態は不明瞭です。
そこで熱力学第一法則を利用してヘルムホルツ自由エネルギーの意味を理解してみましょう。
まず等温条件下において系が状態A \((T; ~ V_\text{A}, ~ n)\) から状態B \((T; ~ V_\text{B}, ~ n)\) に変化するとき、熱力学第一法則は次式で表されます。
\[ \Delta U = U(T; ~ V_\text{B}, ~ n) - U(T; ~ V_\text{A}, ~ n) = -W + Q \]
ただし、状態変化の前後で系の物質量に変化は無いものとします。
また系を準静的に変化させれば、上記の変化の最中に系がする仕事 \(W\) は等温最大仕事に置き換わるので
\[ \Delta U = U(T; ~ V_\text{B}, ~ n) - U(T; ~ V_\text{A}, ~ n) = -W_\text{max} \big( (T; ~ V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (T; ~ V_\text{B}, ~ n) \big) + Q_\text{max} \]
となります。
このとき吸熱量も最大値になるので最大吸熱量 \(Q_\text{max}\) と呼ばれるのですが…
式(19)が示すとおり、最大吸熱量は操作前後の平衡状態で決まる 内部エネルギー変化 と 等温最大仕事 によって記述されるため、同様に最大級熱量も前後の状態のみで値が定まります。
したがって以降では最大吸熱量を次のように書くことにします。
\[ Q_\text{max} \big( (T; ~ V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (T; ~ V_\text{B}, ~ n) \big) \]
※準静的過程における吸熱量が最大になることは、熱力学第一法則 \(W = -\Delta U + Q\) を最大仕事の原理 \(W \leq W_\text{max}\) に代入することで確認できます。実際に \(Q \leq \Delta U + W_\text{max}\) という不等式が得られ、準静的過程の場合に等号となり \(Q\) は最大値を取ることが分かります。
式(19)における等温最大仕事は式(10)よりヘルムホルツ自由エネルギーで置き換えることができるので、結果次式を導くことができます。
\[ \Delta F = \Delta U - Q_\text{max} \big( (T; ~ V_\text{A}, ~ n) \rightarrow (T; ~ V_\text{B}, ~ n) \big) \]
このようにヘルムホルツ自由エネルギーは内部エネルギーを用いて表すことができたので、実態が明らかになったも同然ですよね。
つまり、ヘルムホルツ自由エネルギーとは系が状態変化する過程で吸収する熱を除いたエネルギーということ。
実際に前述の内容まで一切「熱」の概念は登場しておらず、仕事という比較的計算が容易な物理量のみで議論してきたのでした。
逆にその様な議論を可能にするのがヘルムホルツ自由エネルギーの優れた点であるとも言えるでしょう。
※いや…熱の概念を"除いた"というより「熱」の概念を考える必要がないというのが本質的?これ実は断熱系になっている事に気が付くでしょうか…。「どういう事?」って方はこちらを参照してみて下さい。
ヘルムホルツ自由エネルギーとエントロピーの関係
エントロピーを使うことによって式(21)は系の状態量のみで表すことができます。
系が吸収する熱量 \(Q_\text{max}\) は外部環境の温度と系のエントロピー変化の積 \(T \Delta S\) で置き換えられるので
\[ \begin{align*} \Delta F &= \Delta U - T \Delta S \\[15pt] ( ~ dF &= dU - T dS ~ ) \end{align*} \]
とすることができます。
そして、ヘルムホルツ自由エネルギー自体を
\[ F = U - TS \]
と改めて定義を与えておくことにします。
温度一定条件を付与したヘルムホルツ自由エネルギーの全微分から式(22)に戻ることも確認できます。
\[ \begin{align*} dF &= dU - d(TS) \\[15pt] &= dU - SdT - TdS \\[15pt] &= dU - T dS ~~~ ( ~ dT = 0 ~ ) \end{align*} \]
ヘルムホルツ自由エネルギーの温度依存性
ヘルムホルツ自由エネルギーとエントロピーの間の関係を示したところで、ヘルムホルツ自由エネルギーの温度依存性について説明に移ります。
エントロピーと温度は互いに共役な関係性があり、その考え方としてはそれぞれの積がエネルギーの次元を持っていることです。
実際、エントロピーは \([\text{J/K}]\) の次元を持つので温度を掛けることによってエネルギーと同じ次元 \([\text{J}]\) になります。
ちなみに圧力と体積も積を考えるとエネルギーの次元になりますので共役な関係と言えます。
さてヘルムホルツ自由エネルギーの温度依存性は、式(23)を温度について偏微分することで求めることができます。
\[ \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, ~ n} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, ~ n} - S - T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V, ~ n} \]
エントロピーの温度についての偏微分係数は
\[ T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V, ~ n} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, ~ n} \]
の関係が成立しているので、式(25)は次のように整理されます。
\[ \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, ~ n} = -S \]
理想気体のヘルムホルツ自由エネルギー
式(23)を利用して、理想気体のヘルムホルツ自由エネルギーを求めましょう。
理想気体の内部エネルギーおよびエントロピーは次式で与えられます。
\[ U(T; ~ V, ~ n) = \alpha nRT + n\bar{U}_0 ~~~ ( ~ \bar{U}_0 \equiv U(T_0; ~ \bar{V}_0) - RT_0 ~ )\\[15pt] S(T; ~ V, ~ n) = n\bar{S}_0 + nR \ln \bigg[ \left( \frac{T}{T_0} \right)^\alpha \frac{V}{n\bar{V}_0} \bigg] ~~~ ( ~ \bar{S}_0 \equiv S(T_0; ~ \bar{V}_0) ~ ) \]
ここで、\(\bar{U}_0\)、\(\bar{S}_0\) は定数です。
式(27)を式(23)に代入することで直ちに理想気体のヘルムホルツ自由エネルギーを得ることができます。
\[ F(T; ~ V, ~ n) = - nRT \ln \bigg[ \left( \frac{T}{T_0} \right)^\alpha \frac{V}{n\bar{V}_0} \bigg] + n\bar{U}_0 + n ( \alpha R - \bar{S}_0 ) T \]
【サイト運営 : だいご】
今年で物理化学歴12年目になります。
大学入試2次数学でたった3割しか得点できなかったいわゆる数弱落ちこぼれ。それでも好きこそものの上手なれと言ったところか、学会で最優秀賞受賞したり首席卒業できてしまったので、役に立つ知識を当サイトに全て惜しみなく公開しようと思います。ブックマークをオススメ。